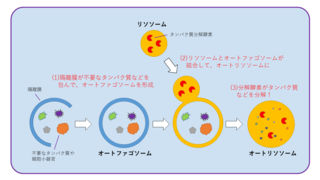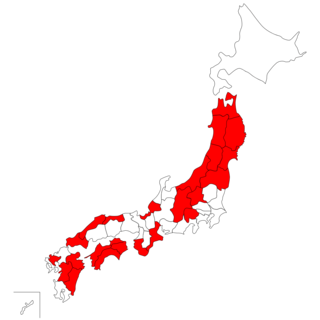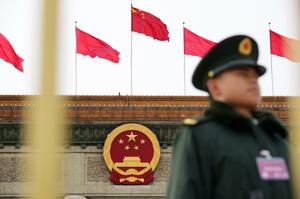この原稿を書いているいま、私は髪の毛を切ったばかりですが、切り取られた髪の毛はそれ以上伸びないし、切ったあとの爪もひとりでに伸びたりはしない。
この髪や爪はやや特殊ですが、仮に私たちが病気、例えば癌に罹ったとして、手術で癌細胞を切除した後、適切に培養すれば「私の癌」は私の体と切り離された後にも分裂、増殖させることができる。また栄養その他を遮断すれば死んでしまうに違いない。
「個体の生死」と別に、このような「細胞レベルの生/死」を考えることができます。
20世紀の半ばに至るまで、私たち人類が手にしていた「死」に関する情報は1つしかありませんでした。
秋になると木の葉が枯れ、茶色くなって落ちる。こういう死を「ネクロ―シス」と呼びます。
都内で開かれた記者会見中に、安倍晋三首相と電話で話す東京工業大学栄誉教授・大隅良典氏(2016年10月3日撮影)〔AFPBB News〕
秋になると食卓にサンマが供せられ、季節を感じたりしますが、焼き魚の身というのも(あまり食事中に嬉しい話ではないかもしれませんが)死んだ細胞、つまりネクロ―シスの状態にある生き物の部品を食べ、それを消化してアミノ酸などバラバラの部品に分解して、私たち自身の体を形作るのに用立てている。
自然界では生きたままの動物の細胞を食べるのが普通ですが、文化的な人類社会では多くの動物性たんぱく質は「ネクロ―シス」の状態で供せられます。干物でも、ハム・ソーセージでも、熟成肉でも、この条件に大差はありません。
逆に野菜サラダなど植物性のたんぱく質は、細胞が生きた状態のまま身体の中に接収することも珍しくない。脇道ではありますが、食と生命を考えるうえで、こういう観点は興味深いものだと長年思っています。
さて、20世紀後半になって、人類はさらに(少なくとも2つ)新しい「死」の概念を獲得します。
第1は、ゲノム科学が進展することで得られた「プログラムされた細胞死」アポトーシス(あえて漢語に直すなら「豁落」とでも言えばいいかもしれません。Apo-離れてptosis落下するというのが原語での意味するところ)という死のあり方です。
これを見出したシドニー・ブレナー、ロバート・ホーヴィッツ、ジョン・サルストンの3人は2002年のノーベル医学生理学賞を分け合っています。