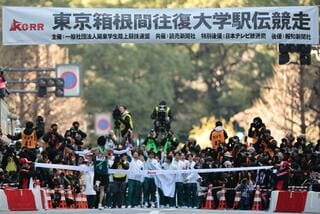アジア開発銀行(ADB)も昨年7月、2010~2030年の長期予測を発表し、経済改革が今後順調に推移すればGDPの成長率が7~8%台に達するとした上で、2030年までに1人当たりGDPが現在の715ドルから3216ドルへと4.5倍になり、中所得国に移行するとの見通しを立てた。
前出の工藤氏も、「国際経済へのアクセスが復活した今、ベトナムで起きたことはミャンマーでも起き得る」とした上で、これまでの「遅れ」は、今後、むしろ「伸びしろ」として認識されるはずだと話す。
しかし、そのためには外資を導入し、衣料品だけでなく、タイやベトナム、マレーシアのように東アジア全体の生産・物流ネットワークに参画し、輸出志向型の経済を確立することが必要となる。それには、外資の導入が不可欠だ。
どの分野にどれだけの投資を誘致すべきか、そしてそのためにはどのようなインフラ整備が必要か――。そう、必要なのは、まさに、国土の将来像を描き、そこに向かう道筋を示す「国家計画」だ。
日本の開発と「全総」
ここで、簡単に日本の歩みと国家計画について振り返っておきたい。第2次世界大戦で国土の大半が焼土と化した日本は1962年、国土の発展に向けた上位計画として「全国総合開発計画」を策定。
高度経済成長や「所得倍増計画」、太平洋ベルト地帯などの工業地帯の発展など、経済復興に焦点を置きつつ国土の発展に努めるという方向性を打ち出した。
また、人口や産業の大都市への集中が問題になり始めた1969年に発表された第2弾となる「新全総」では、新幹線や高速道路のネットワークの整備を通じた地域格差の解消が打ち出された。
その後、1977年には「第三次全国総合開発計画」、いわゆる「三全総」で大都市への人口と産業の集中の抑制が打ち出されたのに対し、バブル景気が始まりつつあった1987年の「四全総」では多極分散型の国土の構築というコンセプトの下、日本各地でリゾート開発などが盛んに進められた。
このように、その性格や内容、位置付けを変化させつつ、55年間の長きにわたり国土計画の道しるべとされた「全総」。
結果として地方の過疎化を生んだという声もあるが、産業の育成をにらみながらあるべき社会インフラの絵姿を示し、国として目指すべき方向性と目標年を明確に掲げた上で、いつ、どのような投資を行うべきか、ターゲットから逆算し明示したことにより、日本のインフラ整備に果たした貢献は大きいと言えよう。