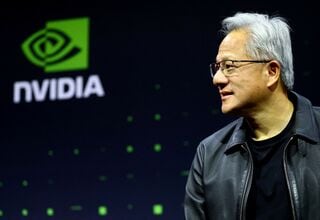リーマン・ブラザースの破綻は世界経済を大混乱に陥れた(写真:ロイター/アフロ)
リーマン・ブラザースの破綻は世界経済を大混乱に陥れた(写真:ロイター/アフロ)
マーケットは株高に沸いている。日経平均株価は急ピッチの上昇をみせ、5万円を超える水準で推移。米国でAI銘柄にマネーが集まる流れを受け、日本でも関連銘柄が持て囃されている。果たしてこの株高に持続性はあるのか。ITバブルからリーマンショックの発生、そして、その後始末まで各国中央銀行の動きを目の当たりにしてきた元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事はどうみるのか。(JBpress編集部)
(神津 多可思:日本証券アナリスト協会専務理事)
リーマンショックによって先進国で最も景気の打撃を受けた日本
今から20年前の2005年、後に国際金融危機と呼ばれる一連の金融市場における大きな調整は、まだその萌芽もあまり認識されていなかった。筆者は2006~2010年の間、主要国の銀行監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会のメンバーだったが、2006年の秋に初めてその会合に出席した時には、まだ不均衡の蓄積が真剣に議論されることはなかったように思う。
しかし現実には、リーマンショックと呼ばれる国際金融危機の種はすでに蒔かれていた。2000年代初めにいわゆるITバブルが崩壊した米国では、政策金利が大幅に引き下げられる中で、住宅ローン金利も低下、住宅価格は上昇を続けていた。
そもそも、ITバブル自体が、当時のFRB議長であったグリーンスパン氏が不合理な熱狂と呼んだブームの結果であった。その反動を和らげるための金融緩和が、次のバブルの温床となったというのも全く皮肉な話だ。
当時、バーゼル銀行監督委員会は四半期に一度開かれていたが、当初、米国からの話は、サブプライム(信用度が低い借り手向け)住宅ローンの焦げ付きが局所的に発生しているというようなもので、国際金融システムの安定を大きく揺るがせるような事態の警告はなかったと記憶している。
それが会合を重ねる毎に、状況認識は深刻になっていった。金融市場でサブプライム住宅ローンの焦げ付きが色々なかたちで伝播し、そのマイナス影響は次第に欧州の銀行にも及んで行った。
2007年にはフランスのBNPパリバのファンドが破綻した。そして翌2008年、米国のベアスターンズの経営が行き詰まり、そしてさらにリーマン・ブラザースが破綻した。
そうした展開の中で、国際金融市場は機能を停止し、その影響は実体経済に及んだ。日本では、金融機関の経営は総じて健全であったにもかかわらず、景気の面では先進国の中で日本経済が負の影響を一番強く受けたのである。