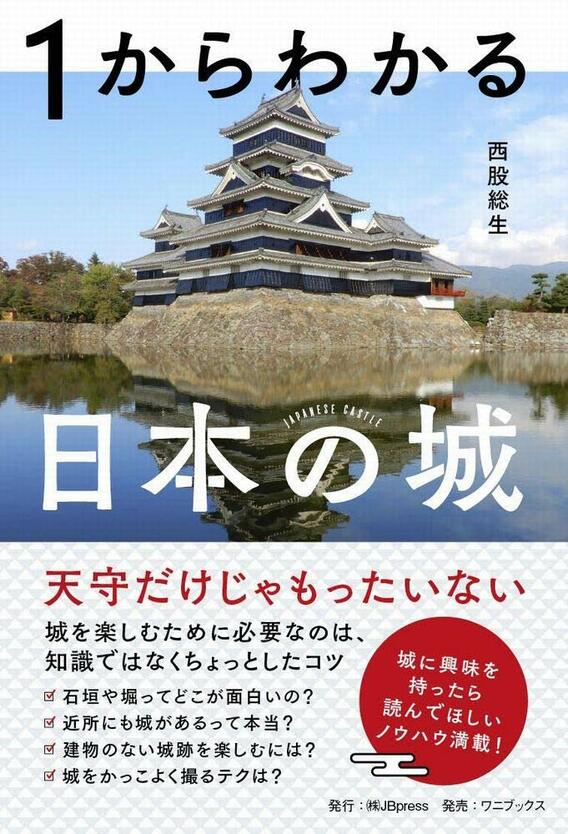撮影/西股 総生(以下同)
撮影/西股 総生(以下同)
(歴史ライター:西股 総生)
はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回は、田沼意次が蒔いた意外な「種」についてご紹介します。
士農工商の枠組みにも穴を開けた自由な空気
前稿「田沼時代、人々は「この国のかたち」を考え始めた…「国学」によって体系化・理論化された思想運動ときっかけ」(8月21日公開)で説明したように、国学は「この国のかたち」を考える思想だから、古典をひもときながら日本の国の成り立ちを明らかにしてゆく。そうすると、もともと日本を「国」として治めていたのは、天皇家であった史実が浮かび上がってくる。
ところが、現実に日本を治めているのは武家の徳川家である。かといって、徳川家は簒奪者であって正当な統治者ではない、などと大っぴらに論じようものなら、謀反人と見なされて手が後ろに回ってしまう。
 愛媛県西予市の卯之町にある高野長英隠家跡。幕政を批判した蘭学者の高野長英(1804-50)は各地に潜行したものの幕府の追っ手にかかって落命した
愛媛県西予市の卯之町にある高野長英隠家跡。幕政を批判した蘭学者の高野長英(1804-50)は各地に潜行したものの幕府の追っ手にかかって落命した
そこで、現実を説明するために案出されたのが、徳川将軍家の大権は朝廷から委任されたものというロジック、いわば「大政委任論」だった。これは、幕府の正当性を説明するのにちょうどよい落とし所だったから、多くの人たちに受けいれられ広まっていった。徳川慶喜が「大政」を「奉還」したのも、こうした認識が前提となっていたわけである。
とはいえ、「大政委任論」が広まるためには、国学が全国に普及しなければならない。いや、その前に、多くの人たちが歴史を学んで議論を繰り返さなければ、国学そのものが体系化されなかったはずだ。
 徳川慶喜が大政奉還を宣言した二条城の二の丸御殿
徳川慶喜が大政奉還を宣言した二条城の二の丸御殿
この、多くの人たちが学んだり、議論をするステージを作り出したのが、自由な経済活動を許容する田沼時代の空気であり、蔦屋重三郎も携わった出版文化の隆盛なのである。出版文化が盛んになったことで、地方の武士や一般庶民に至るまで、書物に触れる機会が増えていったのだ。
大河ドラマ『べらぼう』に登場する、朋誠堂喜三二や恋川春町、太田南畝といった戯作者は武士ではあるが、版元の蔦重とは身分の垣根を感じさせることなく付き合っている。実際、身分家柄にこだわっていたら、多くの人々を楽しませる作品など作れなかったろう。経済の発展と田沼時代の自由な空気は、士農工商の枠組みにも穴を開けていったのだ。
 岡山県北部にある吹屋の街並み。江戸時代後期には各地に町場が栄えて人・物・情報が行きかった
岡山県北部にある吹屋の街並み。江戸時代後期には各地に町場が栄えて人・物・情報が行きかった
とはいえ、武士が統治者で農工商が治められる側、という封建制の基本的枠組みそのものは変わりはない。しかも、この時代は幕府も諸藩も押しなべて財政難に苦しんでおり、飢饉や米不足にも見舞われていた。
となると、世の中をどう治めてゆくかという「経世論」の需要が、武士たちの間で高まってくる。実は『べらぼう』の時代は、各地で藩校の設立ブームが起きていた時代でもあった。しかも、幕藩体制はもともと民政部門が貧弱だったから、民政を充実させるためには民間からの献策も必要だ。こうして、庶民の中でも向学心に優れた者は藩校で学ばせよう、という気運が生じてくる。
 岡山藩池田家の藩校として名高い閑谷学校。備前焼の屋根瓦が美しい
岡山藩池田家の藩校として名高い閑谷学校。備前焼の屋根瓦が美しい
一方で、藩校を充実させるためには、優れた講師も集めなくてはならない。さいわい経済の活性化に伴って、人も物も金も藩や国を越えて動くようになっていたから、それに乗って情報も流通する。この分野ならどこの誰が優れている、という話が伝わってきて藩外からも講師を招聘する。あるいは藩士や領民が他国へ遊学する。
かくて、さまざまな思想や言説が全国に広まり、あるいは交わって、多様な議論が生まれていった。幕末の動乱をへて維新へと結実する思潮の「種」は、田沼時代にひそかに播かれていたのである。ただし、こうした動向は田沼政権にとっては、諸刃の剣ともなった。
 東京駒込の勝林寺にある田沼意次の墓所
東京駒込の勝林寺にある田沼意次の墓所
もともと老中・若年寄を輩出していた譜代大名の中には、成り上がり者の田沼意次を快く思わない者も少なくなかった。彼らは、藩政の危機に直面して経世論を求める中から、藩政改革勉強会とでもいうべきグループを形成していった。やがて、白河藩の改革で実績を挙げている松平定信が、このグループの盟主として嘱望されるようになっていった。
彼らが田沼排斥運動に傾いてゆくのは、必然の流れだったといえるだろう。
 白河小峰城(福島県)。松平定信は白河藩主として改革の実績をあげていた
白河小峰城(福島県)。松平定信は白河藩主として改革の実績をあげていた
*以下の関連記事もご参照ください
「「米不足」に足をすくわれた田沼政権、引き金となった「天明の大飢饉」を悪化させた最大の要因」