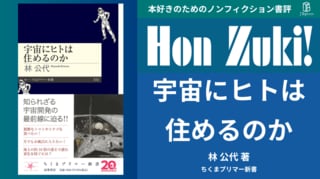ダービー出走の夢は叶わず
マルゼンスキーの出自をたどると、父馬がニジンスキー(13戦11勝。英国クラシック3冠制覇の名馬)、母馬の父がバックパサー(31戦25勝。20世紀の米国名馬の第14位に選出された殿堂馬)という超良血で、生まれる前から話題となり、母馬(シル)は当時30万ドル(当時のレートで8400万円)という高額で落札、日本に持ち帰る総費用は1億2000万円かかったそうです。
マルゼンスキーが生まれた1974年の有馬記念の1着賞金は4000万円ですから、いかに高額だったかわかります(2025年の1等賞金は5億円)。
当時、国産馬の生産保護のため外国産馬やマルゼンスキーのような持込馬にはレース制限が設けられていて、クラシックレースはもとより、今でいうG1レースのような大きなレースには有馬記念以外に出走できませんでした。特にマルゼンスキーの現役期間(1976~77年)では出走可能なレースは全体の1割程度しかなかったのです。
結局、大きなレースでめざせるものは宝塚記念と有馬記念くらいで、マルゼンスキー陣営が当時日本一決定戦でもあった有馬記念を目標としたのも当然の成り行きでした。マルゼンスキーの引退後、1984年から持込馬の制限が撤廃されますが、そこにはマルゼンスキーの存在が大きく影響していたことは間違いないでしょう。
競馬ファンの誰もがマルゼンスキーがクラシックレースでどんな激走を見せてくれるのかを期待していましたが、こうした規制に阻まれ、マルゼンスキーのクラシックレース出走の夢が実現することはありませんでした。
ダービーが来るたびに思い出す有名な言葉があります。マルゼンスキーの全8レースに騎乗し、その強さを最も知る男、元騎手・調教師の中野渡清一、36歳のときの言葉です。
「賞金なんかもらわなくていい。28頭立ての大外枠でいい。ほかの馬の邪魔もしない。この馬の力を試したいからマルゼンスキーにダービーを走らせてやってくれ。出走させてくれればどれが日本一かわかる」
出走できないことへの無念さとマルゼンスキーに寄せる愛情が、ひしひしと伝わってきます。
この年のダービーはラッキールーラが優勝しましたが、マルゼンスキーの出走しないこの年のダービーを「敗者復活戦」と揶揄するファンたちがいました。
クラシックレース3冠目の菊花賞をレコードで制したのはプレストウコウで、この年の最優秀4歳牡馬に選ばれていますが、このレースの5か月前に行われた日本短波賞でマルゼンスキーは7馬身の差をつけてプレストウコウに圧勝、影さえ踏ませることがありませんでした。
日本短波賞の翌月、7月24日に札幌競馬場で行われた「短距離ステークス」(ダート、1200メートル)がマルゼンスキーの最後のレースとなりました。2着馬に10馬身の差をつけるレコード勝ちでした。
その後、陣営は年末の有馬記念をめざし、さらに翌年は凱旋門賞とワシントンDCインターナショナル出走という大きな構想を抱いていましたが、故障を発生したため、海外遠征は夢のまま終わり、翌年1月に引退に至りました。