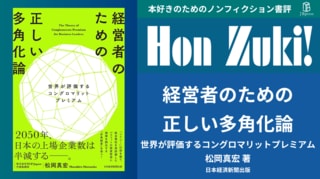歴史の教訓
本書第1章では、第一次世界大戦の「歴史の教訓」がどのように当時の政策主体に理解されていたかが記述されます。
直前の敗戦ドイツに対する戦後処理が次の戦争を招いたという「事実」をどう受けとめるか。その後を知るわれわれは、なにをすべきかするべきでないかを容易に決められそうな気がしますが、その場にいたひとたちは迷います。過去の歴史に学ぶのはよいとして、どの部分をどう学ぶのか。
朝鮮戦争での従軍経験のある歴史・政治学者アーネスト・メイ(ハーヴァード大学)は、戦後米国外交の事例研究をもとにいまや古典となった『歴史の教訓―戦後アメリカ外交分析』という本を著し、政策意思決定にあたって組織や個人が活かす、あるいは囚われる歴史について分析をおこないました。
政治家や企業経営者はよく歴史に学ぶと言いますが、そこで語られる歴史とはなにか、よく考えるとわからなくなります。そんな時に、本書における国務省関係者が歴史から得た教訓と、第2章に出てくるウッドロー・ウィルソンに共感しつつもその問題点を補おうとしたローズヴェルト大統領(FDR)の考えが重なりつつも異なっていることを示したところは、とてもよい事例を提供しています。
それぞれに異なる「教訓」を得たうえで議論している時、どうソリューションを見つけるのか。企業(あるいはすこし大きめの組織)で働いていると、過去の事案を関係者が異なった意味で解釈していることはよくあることではないでしょうか。
「専門家」の役割
いまもそうですが、当時の日本専門家といわれる人たちの政府・官僚機構内での発言力は大きくありませんでした。あたりまえです。米国にとってはヨーロッパにおける戦争の帰趨がもっとも重要であり、日本との戦争にハイレヴェルでリソースがさかれるようになったのはドイツ降伏後のことでした。
ただ、日本にとって幸運だったのは、明治維新よりも前からの文化に興味を持つひとたち、大正デモクラシー期の政治体制・過程を理解しているひとたちが、米国エリート層に少数ながらずっと存在していたことです。(英国のジョージ・サンソム卿もそのひとりと言ってよいでしょう。)
煩瑣になるので個人名は挙げませんが、本書に登場する日本「専門家」(その多くはいまでいう人文知に携わるひとたちで、学者にも行政官にもいました)の多くは、戦時において国務省やOSS(CIAの前身)などで働きましたが、その専門分野を超えて多くの提言を行いました。
その、日本というそれなりに文明的な国を崩壊させてはいけないという、高いモチベーションがどこからきていたのかについて、本書はかならずしも十分な説明を与えてはいませんが、それら専門家の一定数は日本で生活したことがあり、日本人の多様性について理解がありました。
専門家は、米国政府内の力学の変化によって、重用されたり煙たがられたりします。
実際の政策立案において主導的な役割を果たすのはごく少数のひとたちです。それでも多くの専門家は、学問的良心にしたがってみずから信じる最善の助言を行います。第一次大戦後の「歴史の教訓」をふまえてつくられた外交評議会(Council of Foreign Relations)は、大学とならんで専門家たちを安定した環境で研究させる環境を作り出しました。そのような環境あってこそ専門知の有用性が生まれることに気づきます。