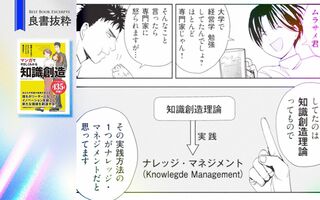経営学と哲学や宗教とに類似点があるのは偶然ではない
西田の哲学は形而上学的な枠組みとして、鈴木の思想は禅仏教の直接的な悟りの論理として発展したものと、アプローチの違いはありますが、両者とも、矛盾を内包することが根本的な実在のあり方だと考える点で共通しています。
これを西洋哲学的に言えば、「正(テーゼ)」「反(アンチテーゼ)」「合(ジンテーゼ)」の三段階のプロセスを繰り返すことで、より高次の真理や理解に到達する、ヘーゲル哲学における弁証法に似た考え方と言うことができます。
そのため、特に西田の「絶対矛盾的自己同一」は、しばしば弁証法と比較されます。しかしながら、直観的・体験的な理解を重視し、矛盾や対立をそのまま受け入れ、それを超えて新たな理解や真理に到達しようとしている点において、論理的・分析的なプロセスを通じて矛盾を解消・統合し、発展を目指す弁証法とは決定的に異なっています。
いずれにしても、こうした経営学と哲学や宗教とに類似点があるのは単なる偶然ではなく、経営が人間の営みであり、企業が人の集合体である以上、必然的なものだと言うことができます。
野中が、経営とは「生き方(a way of life)」だと断言したのは、正にそうした理由からなのです。
ですから、ビジネスがファクトやロジックという「真」に立脚するのは当然として、生きる上での倫理や美学に関わる「善」や「美」がビジネスに求められるのもまた必然なのです。そして、こうした広い意味での哲学を、経営学の言葉で言い換えるなら、それは「経営理念」や「パーパス」に他なりません。
こうした哲学を企業経営に生かせないかと考えているのが、「新しい実在論」のマルクス・ガブリエルです。彼は、企業が倫理的価値と経済的価値を統合することを通じて持続可能な社会の構築を目指す「倫理資本主義」を提唱しています。そして、ドイツの経済界と連携しながら、企業内に経営判断に倫理的視点を組み込む役割を担う、最高哲学責任者(CPO:Chief Philosophy Officer)のポジションを設けることを提案しています。
日本においても同様の動きがあり、例えば、初の哲学コンサルティング会社であるクロス・フィロソフィーズを立ち上げた吉田幸司は、哲学の専門知を活用した組織開発や人材育成、経営者コーチング、社会課題のリサーチなど、多岐にわたる事業を展開しています。