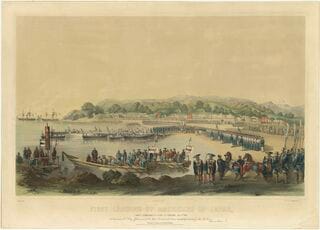アフリカから見えてくる新しい思想がある(写真:Rokas Tenys/shutterstock)
アフリカから見えてくる新しい思想がある(写真:Rokas Tenys/shutterstock)
私たちは、アフリカからどんな知的・文化的影響を受けてきただろうか。いわゆる「アフリカ性」や「アフリカらしさ」とは何だろうか。アフリカに住む人々と、アフリカ以外に住む「アフリカン」と呼ばれる人々はどのように異なるのか。考えれば考えるほど、アフリカという概念は漠然としている。
明らかなことは、日本人はさほど積極的にアフリカについて知る努力をしてこなかったということだ。だからこそ、アフリカを通して、私たちは新しい価値観や思索を深めることができるかもしれない。果たしてアフリカ的な世界観とは何なのか。『アフリカ哲学全史』(筑摩書房)を上梓した立教大学文学部教育学科教授で哲学者の河野哲也氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)
◎前編:「【西欧の白人社会の中で生きる黒人】「黒人だから運動が得意」「黒人だから性的に旺盛」という眼差しの持つ暴力性」から読む
──「アフリカに哲学はあるのか」「何を哲学と考えるか」ということがこの本の中で繰り返し問われています。なぜこの疑問が重要なのでしょうか?
河野哲也氏(以下、河野):「アフリカに哲学はあるのか」ということ自体が20世紀のアフリカの哲学における重要な問いだったのです。
植民地時代の西洋のアフリカに対する眼差しは、「精神性のない未開の野蛮人」という態度でした。しかし、その後に文化人類学の視点が導入され、現地の先住民と呼ばれる人たちの文化を調べてみると、そこには独自の宇宙観、人類観、道徳観が存在するということが明らかになり、研究の対象となっていきました。
フランスの社会人類学者で民族学者のクロード・レヴィ=ストロースや、アメリカ合衆国の文化人類学者クリフォード・ギアツなどの研究がこれにあたります。
とはいえ、先進国ではない地域の人々は、一定の文化の中で繰り返し同じ生活をしており、「変化や進化がない」とやはり思われがちです。
哲学は、自分自身を批判的に分析して変えていくことだと考えられていますが、アフリカにそれがないとすると、「ずっと昔のままだよね」ということになる。たとえば、伝統的な宗教的規律を頑なに守っていて、その世界観にはそれ以上の進展が見られないような場合です。
そこで、アフリカでは自分たちの考えを批判的に検討して、その結果に何かしらの進展があると言えるかどうかが重要なポイントになります。停滞した社会か、進展があるかが、アフリカに哲学があるかどうかの分け目になるのです。
──アフリカの哲学者や、アフリカの思想に巨大な影響を与えた人々を本書の中で紹介されています。その初期の人として、エチオピアで有神論的合理主義を唱えたゼラ・ヤコブという人物を紹介されています。なぜ彼はデカルトと比較されるのでしょうか。
河野:デカルトと似ているというより、生まれた時代がほぼ同じなのです。デカルトが生まれたのは1596年で、ゼラ・ヤコブが生まれたのは1599年です。ヤコブのほうが長く生きていますが、時代的には重なっていました。
ヤコブと、その弟子のワルダ・ヘイワットは、エチオピアで哲学を展開しました。ヤコブの哲学は、エジプトやアラビア圏の哲学などとは違い、他からの影響があまり見られません。独立した形で哲学を発展させたのです。
ですから、「純粋アフリカ哲学」と呼べるものがあるかどうかは分かりませんが、それに近い形だと言えると思います。いわば「エチオピア哲学」です。
 デカルトが生まれた時代に、アフリカでも哲学者は存在していた(写真:Protasov AN/shutterstock)
デカルトが生まれた時代に、アフリカでも哲学者は存在していた(写真:Protasov AN/shutterstock)
──ヤコブの哲学には独特の主張や特徴なども見られるのですか?
河野:変な言い方かもしれませんが、ヤコブの哲学を読んでみると「普通の哲学」という印象があります。アフリカらしさのようなものを強く感じるわけではありません。