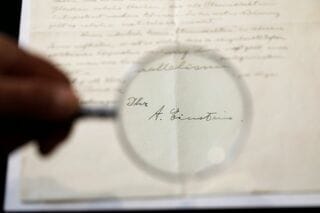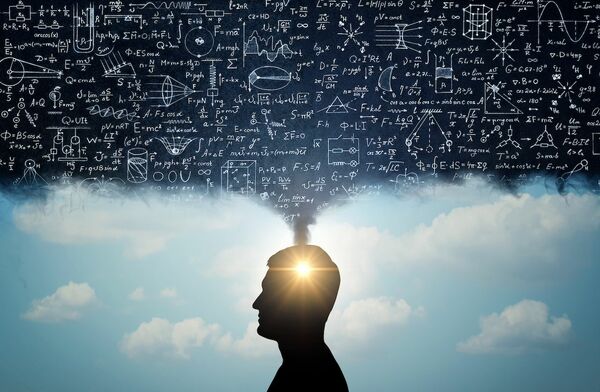 高度な情報社会だからこそ科学的思考が求められる(写真:Triff/shutterstock)
高度な情報社会だからこそ科学的思考が求められる(写真:Triff/shutterstock)
直観的な判断は、時には素晴らしい結果をもたらす。だが、熟慮した末の判断が求められるときも多々あり、人生のすべてを直観だけで決めていくことは危険だ。
こうした熟慮の方法として、ある程度確立された手法に「科学的思考」がある。科学者が研究を進める上で用いる手法だ。自分は科学者ではないから関係ないと目を背けるのも自由だが、科学的思考を日常に取り入れることで、私たちの生活はより安全かつ快適なものになる。科学的思考はなぜ大切なのか、日常でどのように役立つのか──。『科学的思考入門』(講談社)を上梓した植原亮氏(東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授)に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)
──科学的思考は、科学の専門家ではない大多数にとっても大事であると書籍にありました。
植原亮氏(以下、植原):昨今、社会は急激に高度な情報化を遂げつつあります。そのような社会では、科学的思考は極めて重要な意味を持つと思います。
まず、科学的思考は情報を受け取る側に必要な能力です。というのも、今の時代では自分から正解を求めなくても、正解らしい情報が勝手に飛び込んできてくれます。そのような有象無象の情報の中には、当然、怪しげな、時には有害なものも含まれています。
その典型例として、健康情報や医療情報、あるいは政治経済に関わる情報が挙げられます。
そのような怪しげな情報をうまく排除するために、私たちはその信頼性、情報の質を見極めなければなりません。このときに、科学における情報の質や信頼性を高める方法を用いるのが有効だと私は思っています。
次に、高度な情報化により、私たちは情報を発信する側にも容易になり得るようになりました。その際に気を付けなければならないこととして、一定の品質の情報の発信が挙げられます。科学の世界で情報の質を保つための方法を、自らの思考の方法として取り入れることで、質の高い情報発信ができると考えています。
つまり、高度な情報化社会になればなるほど、私たちにとって科学的思考は重要になるということです。
──私たちが普段、無意識に行っている思考と科学的思考には、どのような違いがあるのでしょうか。
植原:科学的思考には複数の方法があり、それらを組み合わせた総合格闘技のようなものだと思ってください。
まず、科学的思考は説明しようと試みるところにポイントがあります。特に、この「説明」は、因果関係、すなわち原因と結果の関係についての説明が核心となります。