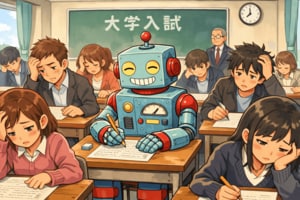明治神宮外苑の再開発計画が、また動き出してきた。事業者は今月、東京都に樹木の保全に向けた見直し計画を提出。東京都の小池知事は「都民の理解と共感を得られるよう事業者にしっかり取り組んでもらいたい」と応じた。イチョウ並木や環境への悪影響が懸念されてきた、この再開発計画。再開発は時に、文化的資源や景観、そこに暮らす人々の生活やコミュニティにも影響を及ぼしかねない。私たちは、これをどうとらえるべきか。人文系の研究者による解説を、2回にわたって紹介する(1回目/全2回)。
(*)本稿は『都市の緑は誰のものか』(太田和彦・吉永明弘編著、北條勝貴ほか著、ヘウレーカ)の一部を抜粋・再編集したものです。
(北條 勝貴:上智大学文学部教授)
「残念石」は誰のものか
本稿執筆中の2024年1月、京都府木津川市に所在する大坂城再建のための石垣用石材の余り「残念石」を、大阪万博のトイレや休憩所に「活用」するという設計案が日本国際博覧会協会主催のコンペを通過、木津川市も同意したという報道がSNSを騒がせた*1。
*1 まとめサイトtogetterにて、関連の意見が整理されている(「『残念石』を大阪・関西万博のトイレに活用する計画への賛否」、2024年3月31日最終アクセス(以下、ウェブサイトの最終アクセスはすべてこの日付とする)。
研究者側から設計者に対し、「指定されているものだけが文化財ではない」といった指摘があり、「トイレに使用するのはナンセンスだ」との一般の批判も高まって、設計者側の文化財認識が問われる事態となったのである。
しかし、そもそも彼らに「残念石は文化財である」との認識がなければ、かかる「活用」案自体が生じなかっただろう。問題は、保全だけではなく活用を推奨した文化財保護法の改変以降、文化財をめぐる認識が多様化し(これ自体は必ずしも悪いことではない)、安易な思いつきでことに当たろうとする関係者が増えている点だろう。
たしかに、石たちが木津川のほとりに人知れず置かれているのは死蔵に等しく(まさに「残念」であり)、万博で活用されれば「残念石」全体の認知度上昇も期待できる。再利用自体に問題があるというなら、例えば国宝の宝庫、奈良の東大寺境内では、前近代の建築物の礎石が庭石等へ無造作に転用されている場合もみられ、それはかまわないのかという意見も出よう。
活用の可否を判断する公共の基準は、一体どこに、誰に属するのか。近年パブリック・ヒストリーの現場で議論になることの多い、Shared Authorityの問題でもあろう*2。
*2 Michael H. Frisch, "From A Shared Authority to the Digital Kitchen, and Back," in Bill Adair, Benjamin Filene, and Laura Koloski, eds., “Letting Go?:Sharing Historical Authority in a User-Generated World," Philadelphia:The Pew Center for Arts and Heritage, 2017, pp. 127-128. および管豊「災禍のパブリック・ヒストリーの災禍――東日本大震災・原子力災害伝承館の『語りの制限』事件から考える『共有された権限』」(標葉隆馬編著『災禍をめぐる「記憶」と「語り」』ナカニシヤ出版、2021年)、拙稿「菅さんの距離感――歴史科学協議会2023年度大会シンボジウムに寄せて」(菅豊先生還暦記念日本民俗学講習会世話人編『記念誌 菅豊先生還暦記念日本民俗学講習会』同会、2024年)参照。
文化財の法的定義
そもそも法律的には、文化財の定義は具体的にすぎ、総括性に欠ける。
文化財保護法の第二条(文化財の定義)には、①有形文化財(第一項第一号)、②無形文化財(同第二号)、③民俗文化財(同第三号)、④記念物(同第四号)、⑤文化的景観(同第五号)、⑥伝統的建造物群(同第六号)について定義があるが、③⑤を除き学術的/芸術的「価値の高いもの」とあって、いまひとつ判然としない。
しかし③に用いられている「我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」、同じく⑤の「我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」との表現からすると、その共通項は、「日本国民の生活・文化を理解するうえで不可欠の事象」と整理できようか(もちろん、「国民」という表現には留保が必要である*3)。
*3 「G-GOV法令検索」で閲覧できる。「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)」。「国民」の問題については、拙稿「国家の前提化を放棄する想像力」(方法論懇話会編『療法としての歴史<知>――いまを診る』森話社、2020年)参照。
2007年には、文化庁が「歴史文化基本構想」を立ちあげ、文化財を活かしたまちづくりを提言したが、新自由主義的発想から保全より活用(観光)にウェイトを置いている点、博物館やアーカイヴズ、大学の現場から不安の声も聞かれた。
しかし、2011年の東日本大震災で、人間のみならず文化財も消滅の危機に直面、以降も列島各地で毎年のように激甚災害が生じるなか、未指定のものも含めてまずは保全を心がけ、可能な範囲で活用してゆこうという方針が採られるようになってきた*4。
*4 近年、この種の出版も相次いでいる。例えば、久末弥生『都市災害と文化財保護法制』(成文堂、2020年)、早川泰弘・髙妻洋成・建石徹編『文化財をしらべる・まもる・いかす――国立文化財機構 保存・修復の最前線」(アグネ技術センター、2023年)、髙妻洋成・小谷竜介・建石徹編『入門 大災害時代の文化財防災』(同成社、2023年)、天野真志・松下正和編『地域歴史文化のまもりかた――災害時の救済方法とその考え方』(文学通信、2024年)など。