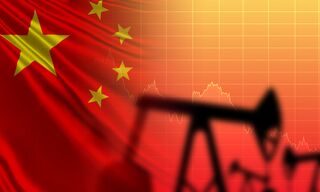メキシコ湾をハリケーン「フランシーヌ」が襲い原油生産に支障が出ているが、中国の需要減退などで価格下落圧力が強い(写真:ロイター/アフロ)
メキシコ湾をハリケーン「フランシーヌ」が襲い原油生産に支障が出ているが、中国の需要減退などで価格下落圧力が強い(写真:ロイター/アフロ)
原油価格の下落傾向が強まっている。10日は一時65.27ドルと約1年4カ月ぶりの安値を付けた。相場の動きが2008年の世界金融危機や2020年の新型コロナウイルス禍のときと似てきているとの指摘もある。世界の景気後退入りを先取りしているのだろうか。
(藤 和彦:経済産業研究所コンサルティング・フェロー)
米WTI原油先物価格(原油価格)は今週、1バレル=65ドルから68ドルの間で推移している。10日には一時、65.27ドルと約1年4カ月ぶりの安値を付けた。原油需要に対する懸念が災いして、今月に入っての下落率は約10%だ。
まず、いつものように世界の原油市場の需給を巡る動きを確認しておきたい。
市場のセンチメントが悪化している状況下で買い材料として新たに意識されているのが、熱帯性暴風雨「フランシーヌ」のメキシコ湾への接近だ。
「フランシーヌの予想最大風速は約40m、最大3mの高潮が発生する」と予測されていることから、米メキシコ湾岸の石油・ガス生産企業は操業を一時停止し、作業員を避難させている。
米国政府によれば、メキシコ湾の原油生産量の24%に当たる日量約41万バレル分が既に失われている。これにより、原油価格はバレル当たり2~3ドル上昇しているが、甚大な被害が生じなければ、その効果は一過性にとどまるだろう。
先週まで買い材料だったリビアの政治的対立は収まったが、原油輸出の大半が依然として滞っており、生産も抑制されている。だが、市場はこれに無反応だ。
石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどの大産油国で構成するOPECプラスは5日、10月から予定していた自主減産幅の縮小(日量18万バレル)を2カ月間延期することで合意した。この決定は既に織り込み済みであったため、市場の反応は鈍かった。
自主減産の拘束力が弱いことも影響している。イラクやカザフスタンの生産量は生産枠を超えており、減産幅の縮小の延期が市場に与えるインパクトはほとんどないのが実情だ。
市場では「OPECプラスは12月から増産を開始する」との見方が広がっている。イラクやアラブ首長国連邦(UAE)はOPECプラス以外の産油国にシェアを奪われることを恐れており、減産継続に消極的だと言われている。
2022年にUAEがサウジアラビアの減産方針に反発し、2023年には生産枠を減らされたアンゴラがOPECから脱退した経緯があり、「OPECプラスの結束のためには増産やむなし」というわけだ。だが、12月からOPECプラスが増産に転じれば、原油価格はさらに下落する可能性が高い。