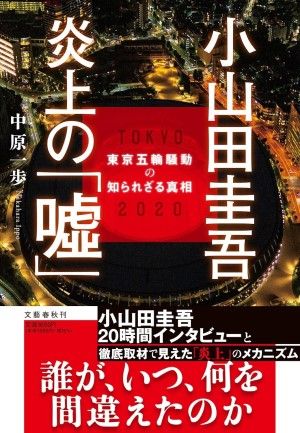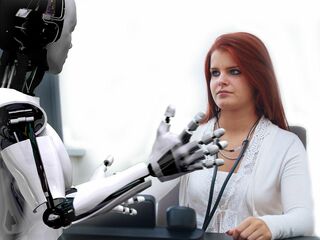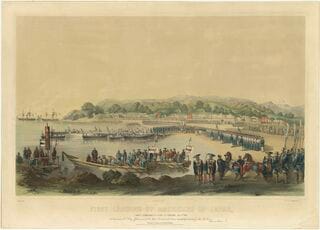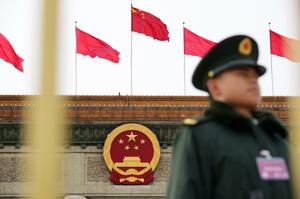客引きが当たって、来日半年で月収が100万円超に
李さんは新宿界隈では名が知られた人物だ。歌舞伎町にやってくる外国人の観光案内をする傍ら、ジャーナリストとしても活躍。生まれ故郷の中国・湖南省の料理を提供するレストランも経営している。2015年、日本に帰化すると、新宿区議選に3度も立候補。残念ながら落選したが、歌舞伎町の表通りは、李小牧さんのポスターで埋め尽くされた。
李さんは、戦後、中国から日本に渡り、横浜や神戸に中華街を拓くなどして日本に定住した「老華僑」に続く第2世代で「新華僑」と呼ばれる。
李さんが来日した頃、日本と中国は留学生を巡って利害が一致していた。中国は鄧小平氏の改革開放政策を契機に日本など国外を目指す若者が増え、日本では国際化のかけ声のもと、中曽根内閣が打ち出した「留学生10万人計画」が進められたのだ。
李さんが暮らしたのは、早稲田通りから神田川に向かって坂を下った場所だった。当時、外国人が借りることができる部屋は限られていた。来日前に中国で稼いだ全財産をはたいて「六畳風呂なし」の安アパートを借りた。当時、日本円で10万円もあれば、中国の地方都市にマンションが買えた時代で、日本と中国の経済格差は圧倒的だったという。
「とにかくカネのために働きました。ラブホテルの清掃員をしながら、外国人向けの職安で紹介してもらったティッシュ配りなどのアルバイトを掛け持ちしました。その後、歌舞伎町で外国人をストリップ劇場や風俗店に案内し、チップを稼ぐ客引きが当たって、それで歌舞伎町案内人と呼ばれるようになったのです。来日して半年で、月収が100万円を超えました」
「危険な日本の街」歌舞伎町を避けて
李さんのように新天地を目指し、日本で成功した中国人は多い。こうした立身出世の物語が「歌舞伎町」だったことも興味深い。高田馬場は「新宿区の文教地区」であると同時に「東京最大の大歓楽街」歌舞伎町にも隣接しているのだ。
歌舞伎町の歴史は、戦後の新宿、東京の歴史そのものだ。空襲で焼け野原となったこの一帯を、劇場、映画館、演芸場、ダンスホールなどの大衆娯楽を中心とした歓楽街として再生させる計画が立てられたのは終戦直後。やがて、新宿駅という巨大ターミナルに隣接した歌舞伎町には、仕事を求めて全国から若者が押し寄せる。いわゆる、出稼ぎ労働者だ。
働く現場が「歌舞伎町」ならば、その周縁に、この街で働く人々のベッドタウンが誕生するのは時間の問題だった。何しろ「眠らない街」の住人だ。仕事が終わるのは公共交通機関が動いていない夜明け前。歩いて帰ることができて安家賃である必要がある。1980年代以前、歌舞伎町の住人は、日本各地のいわゆる「地方」から、一攫千金を夢見て上京してきた出稼ぎ目的の国内移住者だった。
こうした人々の寝床となったのが、いわゆる「四畳半、木造、風呂・トイレなし」の木賃アパートだ。こうして、歌舞伎町の周縁の高田馬場、新大久保に木賃アパートベルトが形成される。
確かに、歌舞伎町と新大久保を隔てる職安通りを挟んで、新大久保側には今でもトタン屋根のアパートが点在している。こうした安宿は、早稲田大学に通うため上京してきた学生にも好都合だった。早稲田通りから谷を下った場所を流れる「神田川」。そう1973年(昭和48年)、シンガーソングライターの「南こうせつとかぐや姫」が歌って大ヒットした「神田川」の舞台も、この一帯だった。
しかし、1990年代に入ると歌舞伎町は不良中国人の巣窟となり治安は悪化する。ルーツを同じくする中国人が日夜、勢力争いを繰り広げ抗争に発展。中でも1994年の「快活林事件」は歌舞伎町、そして、中国人のイメージを決定づけた。長年、歌舞伎町で飲食店を経営する男性は当時をこう振り返る。
「日本のヤクザも怖いけど、中国人同士の抗争はとにかく派手だった。数十人のグループが武器を手に乱闘を繰り広げました。この事件の直後ですよ。歌舞伎町に『怪しい中国人を見かけたら110番』と書かれたポスターが警察によって張り出されたのは。この街が、このイメージを払拭するのには十数年の年月がかかりました」
この事件の舞台となったのが「快活林」という名前の中国料理店だった。このニュースは中国本土でも大々的に報じられ、中国人にとっても歌舞伎町は「危険な日本の街」の代名詞となった。
しかし、当時、高田馬場の治安は先述した通り、保たれた。そして、30年の歳月が経過した今、高田馬場は世代も価値観も全く異なる中国人が多く暮らす街となった。
早稲田大学留学センターによると、2023年11月の外国人学生在籍数は6133人。そのうち中国籍の学生は3420人と全体の半数以上を占める。また、中国人に追いつけ追い越せと、アジアでは韓国人、台湾人、インドネシア人、タイ人が続く。
かつて早稲田通りが「ラーメン街道」の異名をとる時代もあった。人気店が競って出店し激戦区を形成。また、学生相手のデカ盛りで有名な大衆食堂は「ワセメシ」と呼ばれ愛された。ただ2000年代以降、都心部の地価高騰、店主の高齢化、後継者不足などの理由で、これらの店は姿を消しつつある。そのかわりに「ガチ中華」が増えているというわけだ。
いつの時代も「安くて、早くて、旨い」食堂は、学生街にはつきものだが、その風景は様変わりしつつあるようだ。
中原一歩
(なかはらいっぽ) ノンフィクション作家。1977年佐賀県生まれ。社会や政治について雑誌、Webで執筆。潜入事件取材からお笑いの考察まで幅広くこなす。ライフワークは「食と職人」のルポ。『最後の職人 池波正太郎が愛した近藤文夫』(講談社)、『私が死んでもレシピは残る 小林カツ代伝』(文藝春秋)、『マグロの最高峰』(NHK出版)、『㐂寿司のすべて。――本当の江戸前鮨を食べたことがありますか?』(プレジデント社)、『寄せ場のグルメ』(潮出版社)、『小山田圭吾 炎上の「嘘」 東京五輪騒動の知られざる真相』(文藝春秋)など著書多数。
◎新潮社フォーサイトの関連記事
・三中全会「中国式現代化」の“分からなさ”は習近平式ガバナンスの重要ヒント
・高まる原子力への期待と燃料サイクルにおける課題
・殺人犯・クラシコフの釈放に固執したプーチン政権の損得勘定