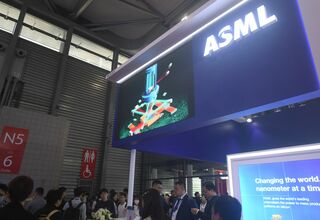「高田馬場は新宿と池袋に挟まれた好立地なのに家賃が安いのです。それに、同じ同胞とはいえ、新宿や池袋は、すでに日本にいる中国人年配者が幅を利かせている。彼らとはビジネスに対する考え方も、文化慣習も全く違う。そうした、縦社会のしがらみが高田馬場にはない。自由にのびのびと商売ができるのです」
この日、私は劉さんの話を聞くことを目的に店を訪れたのだが、いつの間にか食卓には所狭しと料理が並んでいた。しかも、どれも店のメニューにはない豪華なものばかり。あしらいの野菜にまで飾り包丁が施されている。店で働く中国人はいずれも、名だたるレストランで働いていた強者らしい。
「これは私の故郷で、客人を接待する料理です」。蒸した鶏肉を皮ごと薄切りにして、香辛料のたっぷり入った甘辛いソースをつけて食べる前菜や、豚の三枚肉を黒酢のタレで煮込んだ料理は絶品だった。しかし、唐辛子がふんだんに使われた大皿料理を、一人で平らげるのは辛かった。帰り際、劉さんが興味深いことを教えてくれた。
「中国でも新宿、池袋といえば怖いというイメージがあります。けれども、高田馬場にはそうした暗さがない。それに地元の人も中国人に対する偏見がない。真面目にビジネスをしようと思う中国人にとって、この街はとても暮らしやすいのです」
漢字圏の人間にとって親しみやすい町名
高田馬場銀座商店街振興組合・理事長代行の杉森昭祐さんも、高田馬場の「治安の良さ」を強調する。杉森さんは1942年生まれ。組合の最古参の一人だ。戦前に母親が創業した紙問屋を戦後、引き継ぎ、文具店として再建。地元で愛される店として半世紀近く営業を続けてきた。
しかし、数年前に体調を崩したことをきっかけに、早稲田通りに面した店舗そのものはやめてしまった。今でも昔なじみの客から注文を受け、細々と商売は続けている。
「高田馬場が中国人を含むエスニックタウンになったのは、この十数年の出来事です。山手線の隣駅の新大久保は1980年代以前から中国や韓国、イランなど中東の人が集まる街だった。今でこそ韓流の街として観光地になっていますが、当時は派手なネオンが瞬く怪しげな店も多く、ちょっと怖いというイメージがありました。一方の高田馬場は早稲田大学の最寄駅。教育の街であり、表通りは地域密着の店舗ばかりでした。だからこそ、そうした怪しげな店が流入する隙間がなかったのです」
確かに高田馬場の駅前には、学生相手の金貸し業の看板や、派手なネオンの大人の社交街こそあったものの、街の治安、秩序は保たれていた。
しかし、私がこの街に、ある意味での「寄せ場感」を感じるのは、この高田馬場の多国籍化の歴史が、東洋一の歓楽街と呼ばれた新宿・歌舞伎町と深い関わりがあるからだ。事実、30年ほど前まで、駅前には日雇い労働者に仕事を斡旋する「手配師」の姿があった。
「高田馬場は中国人など漢字圏の人間にとっては親しみがあるんです。東京のど真ん中にあるのに、名前に『田』とか『馬』が入っているでしょ。なんだか暮らしやすいイメージがある。事実、私も私費留学で来日した際、最初に暮らしたのが高田馬場でした」
そう語るのは、歌舞伎町案内人の異名で知られる李小牧さんだ。
◎新潮社フォーサイトの関連記事
・三中全会「中国式現代化」の“分からなさ”は習近平式ガバナンスの重要ヒント
・高まる原子力への期待と燃料サイクルにおける課題
・殺人犯・クラシコフの釈放に固執したプーチン政権の損得勘定