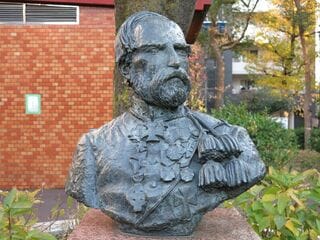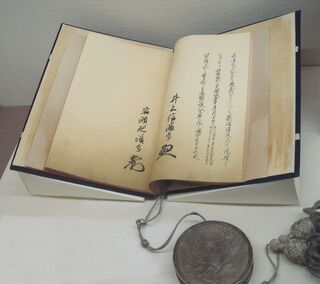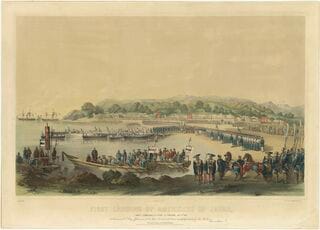斉彬・西郷による幕府への周旋活動
安政4年12月25日、斉彬はハリスの出府、通商条約の審議や南紀派の動向といった情勢変化に着目し、幕府に建白書を提出した。この中で、将軍継嗣は血統が重要であると
残り1611文字
安政4年12月25日、斉彬はハリスの出府、通商条約の審議や南紀派の動向といった情勢変化に着目し、幕府に建白書を提出した。この中で、将軍継嗣は血統が重要であると
残り1611文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら