回して遊ぶ「ネジチョコ」ヒットに見る、デジタル化で歯車が回った中小製造業
【公庫総研と考える】ためらうのも無理ないが、踏み出してこそ生まれるゆとり
2023.11.21(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

ローカル線廃線跡、そのまま残した駅舎とレールに人が訪れるようになったワケ
【後編】テーマパーク化しない、山間地の廃線活用…シンクタンク研究員に聞く
河合 達郎
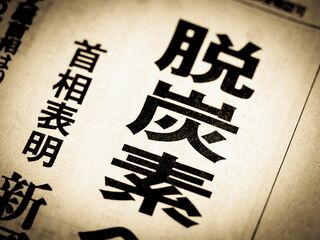
“年商数倍”の例も…なぜ脱炭素ビジネスは中小企業こそ「相性がいい」のか
【公庫総研と考える】カーボンニュートラルの成否を決める脱炭素ビジネスの今
原澤 大地

最初の空き家で失敗…不動産業が成立しない過疎地で築いた空き家活用スキーム
【公庫総研と考える】薩摩半島南端の町がたどり着いた“三方よし”の利活用術
桑本 香梨

なぜ移住者の商売に地域は冷たいのか?「田舎は閉鎖的だ」では何も解決しない
【公庫総研と考える】地域に「なじんだ」人ほど黒字に、引き返す選択肢も必要
桑本 香梨

山林90%・人口3千人…道北の町のローカルベンチャーはなぜ成功するのか?
【公庫総研と考える】「伴走支援」「事業承継」移住創業を後押しする小さな町
桑本 香梨
日本の中小企業 バックナンバー

和菓子店を継いだ工場長に突如訪れた試練、長年一緒に働いた仲間は次々と離職…親族外への事業承継、成否分けるカギ
日本政策金融公庫総合研究所

なぜ米穀店が地元の人気カレー店を継ぐことになったのか?親族外への事業承継で受け継がれる、中小企業の想いと価値
日本政策金融公庫総合研究所

“脱東京”で年商4倍を実現、福井に移転した中小企業はなぜ多角化に成功したのか?地方移転の成否を分けるポイント
日本政策金融公庫総合研究所

和歌山生まれの「アナウンサードローン」、開発したのは東京からの移転企業だった…じわり広がる企業の“脱首都圏”
日本政策金融公庫総合研究所

岩手最古の酒蔵を生まれ変わらせたのは27歳・Uターン・日本酒初心者の女性だった
岸 美雪

「とりあえず殺虫剤」とは一線、虫の声を聴く男が挑む、生き物との共存ビジネス―長崎発、害虫駆除の新たな哲学―
栗下 直也



