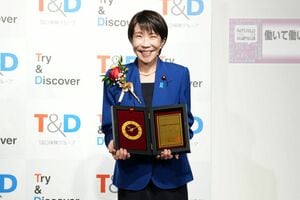仕事の「絶対量」は天然資源のように限られていない
もう1つの要因は、AIは雇用を奪ったりはせず、誰を雇用して何の仕事を任せるかを決めるのは人間自身であることです。『雇用の未来』が指摘した内容についてメディアな
残り3141文字
もう1つの要因は、AIは雇用を奪ったりはせず、誰を雇用して何の仕事を任せるかを決めるのは人間自身であることです。『雇用の未来』が指摘した内容についてメディアな
残り3141文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら