ドイツがゴリ押ししたEU「合成燃料」容認は「エンジン車の寿命」を延ばすのか
欧州自動車業界の開発戦略や政府政策の中心はあくまでもBEV
2023.4.27(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

所得や社会的ステータスが高い人ほどCO2排出量が多くなる「納得の理由」
ライフスタイルがCO2排出に及ぼす影響、「性別」「年齢」「食生活」でも差あり
篠原 拓也

充電器の設置はなぜ進まないのか?EV購入の前に知っておくべきインフラの実態
高額見積もりに設置を躊躇する事業者、故障中のまま放置のEV充電スポットも
桃田 健史

欧州の全面EVシフトに「待った」、EUの政策に注文つけるドイツメーカーの本音
エンジン車存続のための妥協案「e-fuelの導入を」
桃田 健史

EUの次期排ガス規制案になぜか猛反発するイタリア、その本当の理由
極右ポピュリストのメローニ首相の狙いは産業界と支持者向けのアピールか
土田 陽介

復活したマツダのロータリーエンジン、大方の予想に反していた「使い方」
エクステンダーではなくシリーズハイブリッドだった「MX-30 e-SKYACTIV R-EV」
桃田 健史
本日の新着
自動車の今と未来 バックナンバー
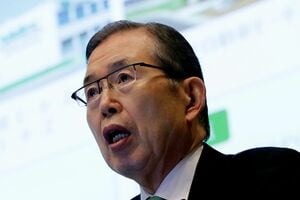
ニデックにアクティビストの影、ガバナンス不全で永守氏の院政も…“イエスマン”の社外取では「第2の創業」は遠い
井上 久男

【試乗レポート】スバル新型「フォレスター」で1400km!ストロングハイブリッド、ガシガシ系を卒業した6代目の実力
桃田 健史

【2026年の自動車業界】破談から1年、日産とホンダは再統合へ向かうのか──技術提携だけでは埋まらない課題
井元 康一郎

【2026年の自動車産業】中国に負ける日本、ハード・ソフトで圧倒的な差も…現実を直視し技術を「盗み返す」べき理由
井上 久男

日本で販売減のボルボ、だが改良版「XC60」1200km試乗で見えた“静かなプレミアム”路線の強み
井元 康一郎

川崎市が挑む「モビリティハブ」、静かに進む都会の「陸の孤島化」の救世主になるか?
桃田 健史







