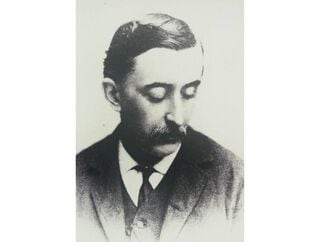遊郭全焼、そして消滅
慶応2年(1866年)「豚屋火事」で横浜開港場は大火に見舞われた。
火元は日本人町の豚肉屋鉄五郎宅。炎は勢いを増し、日本人町の3分の1、外国人居留地の4分の1を焼き払い、港崎遊郭も全焼。
400人以上もの遊女たちが港崎遊郭から逃げ遅れ焼死した。
その後、遊郭は何度か大火で移転し、吉原町遊廓、高島町遊廓、永真遊廓など、名称が変わった。
明治5年(1872年)、遊郭が吉原町遊廓に移行すると、娼婦を取り締まるための鑑札は役目を終えて、在住地官長への届け出制となった。
未解決のまま棚上げされていた混血児の国籍問題は、その目途がつかないうちに江戸幕府は終焉。
そして明治政府は明治5年(1872)戸籍法の布告により、混血児の出生後の国籍は、父母いずれかの国籍に属さねばならなくなったため、出生を届けさせることを規定とした。
明治6年(1873)政府は日本人と外国人結婚許可の法令を発布。
鎖国時代から安政の開国を経て、この法令が出るまでの約200年の間、わが国の女性は外国人男性と対等な地位など望めるはずもなく、常に傅(かしず)き続けなければならなかった。
港崎遊廓は豚屋火事により港崎町から撤退を余儀なくされ、その後の復興計画もなく、港崎町そのものが姿を消した。
代りにその跡地に大きな洋式公園を造り、そこから港へ続く幅の広い大通りを造る都市計画が浮上。
公園の設計は、「日本の灯台の父」と讃えられる英国人技師リチャード・ヘンリー・ブラントンをはじめとする外国人が中心になって行われた。
横浜公園が完成した当時、居留地外国人である「彼」と日本人である「我」の双方が使える公園という意味から「彼我公園」と呼ばれた。
しかし、実際には野球場とクリケット場を兼ねた居留している異人のための運動場というのが実情であった。
その公園から港に向かって日本初の西洋式街路・日本大通りが開通すると、神奈川県庁などを有する横浜の中心部となった。
横浜が開港し男尊女卑の世の中で、羅紗緬たちの運命は、翻弄され、愚弄されながら、時代の波とともに消えていった。
日本は鎖国から開国となった激動の時代、外交や外貨獲得の手段として、日本を支えた多くの名もなき女性たちの記憶を留めるものに、遊郭の遊女が信仰した「岩亀稲荷」が横浜市西区の岩亀横丁の中ほどに現存している。
また、港崎遊郭随一の繁栄を誇った岩亀楼の「石灯籠」は横浜公園内の日本庭園に、いまも、ひっそりと佇んでいる。
それらの遺構は時代に流されながら生きた、ラシャメンたちの徴憑(ちょうひょう)として、その僅かな面影をいまも漂わせている。
 数多くの名もなき女性たちの記憶を留める、この石灯籠には「岩亀楼」の文字が刻まれている
数多くの名もなき女性たちの記憶を留める、この石灯籠には「岩亀楼」の文字が刻まれている
次ページにこれまでの連載