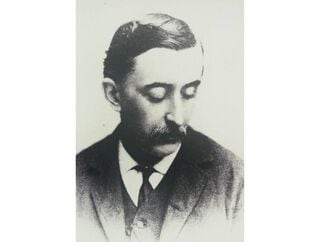だが、時とともに名付け遊女ではない、鑑札をもたない素人のもぐりの羅紗緬が現れた。
そして素人の町娘の斡旋業者の出現により、外国人は職業女出身ではない妾を抱えられるようになるのだが、妾は結婚ではないとの理由から、奉行所はこうした法律の抜け穴を封じることができなかった。
結果、幕府が娼婦を取り締まる手段の鑑札は、なし崩しに有名無実化した。遊郭開業6年目の慶応2年(1866)には異人館通いの羅紗緬は約2500人に達した。
異人と遊女の混血児は
外国人が居留して遊女や素人の女性と接する機会が多くなれば、いきおい、その間に子供が生まれることが考えられる。
江戸幕府が鎖国令を発布したのは横浜港開港の約200年前・寛永十二年(1635)三代将軍・徳川家光の時代、長崎以外の外国貿易および海外渡航は禁止となった。
当時、すでに朱印船の渡航は廃止となっていて、海外渡航者の帰国も禁じていたが、さらに幕府はスペイン、ポルトガル両国人が日本で生んだ子女287人を、長崎から澳門(マカオ)に追放する国外退去命令を発令。
以来、異人と遊女の混血児は、日本に居場所はなくなった。
横浜・港崎遊郭に話を戻そう。文久2年(1862)外国奉行は各国領事に幕府の対策について書簡を送った。
そこには外国人の居留中に雇った日本の遊女が出生の児子は、出生の日から男女にかかわらず、その国(外国人)の国に属し、日本国籍は与えず外国籍に属すると通達。
これに対して各国領事はこぞって反対した。
遊女が生んだ小児に養育金を支払うことは認めるが、それを自国人とみなすことは認め難いというのである。
そして、庶子はその母の属する国籍に入ることは各国法律の一般に定めるところで、仮に日本婦人が正式に外国人と結婚する暁には、自国政府はこれを承認するであろう、と反駁(はんばく)したのである。