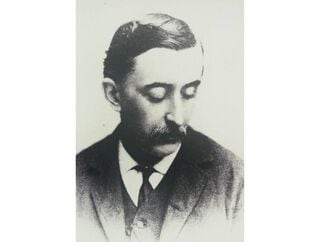幕府は外国人との間に羅紗緬が妊娠することを戒めていたが、そうした事象は、やがて多発することになる。
だが、異人と遊女の混血児の国籍問題は難航した。
とりあえずの措置として幕府は10歳までは日本人として市内に居住できるが、それ以上になると外国人として居留地に移住させた。
異国の居住者は、そのすべてが滞在の任期を終えて本国に帰国する際には、現地妻を捨てて各々の国へと帰っていった。
日本の発展を支えた羅紗緬たち
岩亀楼の一番の美貌の遊女・喜遊太夫は文久2年、ペリー艦隊の軍人に言い寄られ、店主から外国人の一夜妻を命じられたのを拒むと「露をだに 愛ふ倭の 女郎花 ふる亜米利加に 袖は濡らさじ」と辞世を残して自刃。
のちに、その逸話は戯曲として『ふるあめりかに袖はぬらさじ』として上演された。
また、羅紗緬の中には、自分よりはるかに広範かつ該博な知識をもつ、外国から来たパトロンを会話で楽しませる、きわめて知性に富んだ女性もいた。
近代初期の日本外交において薩摩藩と縁が深く活躍したシャルル・フェルディナン・カミーユ・ヒスラン・デカントン・ド・モンブラン伯爵の世話をした「フランスお政」や、幕府の肝いりでフランス軍事顧問団団長のシャルル・シュルピス・ジュール・シャノワーヌ大尉の妾に選ばれた御用羅紗緬「将軍お倉」。
フランスの技師で横須賀製鉄所所長・レオンス・ヴェルニの側妻(そばめ)「お浅」など、時代の波に翻弄されながらも、日本の発展を陰で支えた聡明な羅紗緬も多く存在したのである。