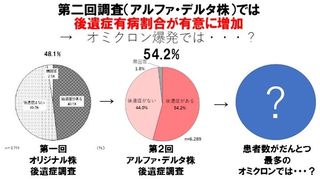(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
新型コロナウイルス感染症の感染極期には、入院できずに自宅で命を落とした方が少なからずいる。なぜ、そのような事態が起こったのか? 今後に活かすべき教訓は何か? 「自宅放置死遺族会」を設立した遺族の率直な声を、讃井將満医師(自治医科大学附属さいたま医療センター副センター長)が訊いた。連載「実録・新型コロナウイルス集中治療の現場から」の第83回。
2020年4月――新型コロナウイルス感染症の第1波極期に、埼玉県内で自宅待機中だったひとりの新型コロナ患者が亡くなりました。それを機に、私は一医師として何かできることはないかと考え、県調整本部(各保健所が管轄内の病院で対処できないときに、管轄をまたぐ入院調整を統括する機関)で入院調整のお手伝いをするようになりました(第1回、第2回参照)。しかし、われわれが全力を尽くしても、その後も自宅療養中に亡くなる方をゼロにすることができず、忸怩たる思いを抱いてきました。
今回は昨年(2021年)9月に設立した自宅放置死遺族会の共同代表、高田かおりさんと西里優子さんにお話を伺います。率直なご意見をいただき、今後の医療体制の改善に役立てたいからです。同時に、ややもすると新型コロナ感染症の緊張感が薄れてきている今、医療従事者も行政も社会の皆さんも「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とならないよう、「何があったのか」を伝える必要があると思うからです。
この時代に「FAXを入れるように」
讃井 高田さんは弟さんが、西里さんはお父様がご自宅で亡くなられました。まず、その経緯からお聞かせください。
高田 私の弟(43歳)は沖縄に単身で住んで居酒屋を経営していました。
昨年の8月10日、大阪府警を通じて沖縄県警から弟が亡くなったという連絡が突然入りました。「なんで?」と思いました。弟とは7月20日過ぎに電話をしていて、その時は元気だったからです。警察の人には、「なにかの間違いです」と言いました。ですから、弟が亡くなった経緯は、保健所の担当者の方から聞いたものになります。