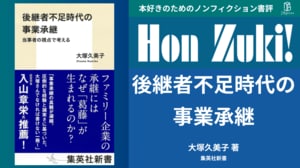開封して三度出会った彼女の後姿。文庫化からすでに1年が経っていた。添えられていた真摯な訴えの手紙は、少なくはない「著者の本の売り込み」のたぐいとは明らかに異なっていた。
自己の作品がいかに優れているかに終始するそれらとは一線を画し、弱者である被害者の側に立って、この問題をどうにかしなければならないという、鬼気迫る「無私」の思いが綴られていたのだった。それでも、まだ本書を読む前の僕は、「スクールセクハラ」という魂の殺人ともいうべき犯罪行為をどこか軽く捉えていた。
様々なハラスメント問題が盛んにメディアに取り挙げられた2018年。この本を売り出すにはいいタイミングかもしれないなと、どこか頭の隅のほうで「計算」していたように思う。
だが心を抉られるような事実が書かれた本書を読み終え、すっかり打ちのめされた気分で、もう一度池谷さんの手紙を読み返して「あぁ」と声が漏れた。この人は、この絶望に近い被害状況を知ってなお、逃げ出すことなく被害者に寄り添い、あまつさえ強大な敵と戦おうとしている。そこに自分を利するものは何ひとつないというのに・・・。
覚醒を促す活動に取り組むことではないか
もし他人の絶望に触れたとき、自分に何ができるだろう。声をかけずに去ることは選択肢のひとつかもしれない。なぜなら知らなければ、自分の認知する世界において、そこに絶望があることにはならないからだ。4年の間、僕のなかに本書の被害者の人たちの絶望は存在しなかった。だが、いまはある。二度、通り過ぎた僕が、三度目にして出会った真実。
何かをしなければならないと思った。