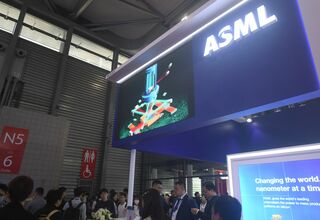だが、何せ会話のスピードが速いし、皆押しが強いので、言葉を差し挟むタイミングも分からない。そのうえ、上海では上海語が普通なので、北京語しかできない僕は何が話されているのかも分からず、会話に入ることもできなくて、せいぜい「おいしいです」くらいしか言うことができなかった。
そうした国籍や性格の問題を抜きにしても、周りが納得も理解もできなかったのは、CAという華々しい仕事をしていた彼女が、なぜこの貧乏日本人と一緒になるのを決めたのかということだった。
「おまえは絶対に騙されている」と本気で彼女に忠告してくれる友人もいたそうだし、彼女のこれまでお付き合いしてきた男性と比較すると、明らかにワンランクどころか、5ランクくらい落ちる僕と結婚すると宣言した彼女をみれば、周りの人間は、彼女が壊れたと思っても至極当然の判断だろう。
逆に僕のほうは、彼女と結婚することを誰にも言っていなかったし、両親すら直前まで僕が結婚することを知らなかったので、特に大きな波風は立たなかった。社会経験、人間性、性格の良さ、経済力、どの点をとっても彼女は僕より優れていたから、伝統的な結婚観に照らし合わせてみれば、ほぼ僕が彼女に嫁いだようなものだと思う。
出会いは飛行機の上で
彼女とは、飛行機の上で知り合った、というとドラマのようでかっこいいけど、それほどドラマチックな展開ではなかった。
そのとき僕は、たまたま実家に戻る大阪行きの飛行機に乗っていた。そこに、たまたま彼女も客室乗務員として乗っていた。彼女は普段、ファーストクラスかビジネスクラスを担当するのだが、その日は同僚が病気で欠員が出たので、エコノミークラスを担当していたらしい。
中国系の航空会社にありがちな、がんがんに冷房が効いている機内で凍えて遭難しそうになっていた僕は、何人かの客室乗務員に「毛布をもらえませんか?」と一生懸命伝えていたのだが、これがまったく通じなかった。英語はまったくできないし、下手くそな中国語では聴き取ってもらえず、最後にはイヤホンが出てくる始末。恥ずかしがり屋で内向的な僕は、まったく必要ないイヤホンを片手に笑顔で「謝謝(ありがとう)」と答えるしかなかった。
そのとき、近づいてきて「何か欲しいですか?」と日本語で声をかけてきたのが彼女だった。サービス用語として「何か欲しいですか?」という日本語は多少問題があるかもしれないが、凍えて唇がやや紫色になりつつあった僕にとっては神の声であり、ようやく必要な毛布を手に入れた僕は彼女に何度もお礼を言った。