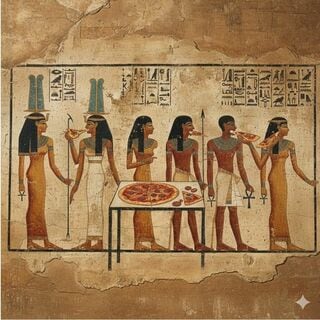「わずか数十件の偽回答」で世論調査の回答を誘導、AIによって無効化されるオンライン調査、抜本的な再設計が不可避
【生成AI事件簿】人間のチェックをすり抜けるための擬態テクニックも驚異的、人間のように振る舞うAIは検出できない
小林 啓倫
経営コンサルタント
2025.11.22(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
増え続ける低俗・低品質な「ゴミ」コンテンツ、生成AIが生み出すスロップの氾濫をどう防ぐ?