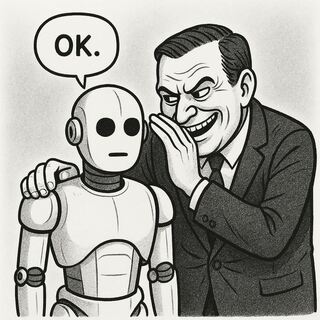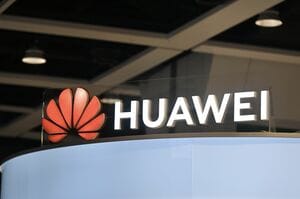「ワークスロップ」を生み出すAIとどう付き合う?(筆者がWhiskで生成)
「ワークスロップ」を生み出すAIとどう付き合う?(筆者がWhiskで生成)
(小林 啓倫:経営コンサルタント)
皆さんは、部下や後輩を教育した経験があるだろうか。あるいは、新しく一緒に働くことになった同僚でも構わない。自分が内容を深く理解している仕事を、それに関する知識が全くない人に教えるというのは、決して楽ではない作業だ。
事細かに指示を出し、出てきた成果物を隅々までチェックして、修正箇所を指示し、再提出された成果物をもう一度チェックする――。これなら自分でやった方が早いと何度も感じてしまうだろう。
ただ、繰り返し教えているうちに、相手も要領をつかんで、徐々に期待通りの成果を出してくれるようになる。こうして彼らは信頼できる戦力として、あなたをサポートしてくれるというわけだ。
もっとも、その過程で、相手が一切成長しなかったとしたらどうだろうか。ある程度の成果物は出してくれるのだが、何度言っても同じミスを繰り返し、チェックが必要になる。そのような状態では、完全に仕事を任せてしまうことなど怖くてできないだろう。
なるべく遭遇したくない話だが、実は多くの人々が、いまこの問題に直面しようとしている。そこで「物覚えの悪い部下」になるのは、おなじみのAIだ。
職場をむしばむ「ワークススロップ」
以前この連載で、「スロップ(slop)」という言葉があることを紹介した。これは英語で「汚水」「残飯」などを意味する言葉なのだが、近年では「価値のないもの」の例えとして、ネット上で使われるスラングとなっていた。それがさらに転じて、最近は「AIによる低品質コンテンツの氾濫」を指して「スロップ」と呼ぶようになっている。
そしていま、「ワークスロップ(workslop)」という言葉が登場した。これは「work(仕事)」と先ほどの「slop」を組み合わせた造語で、スタンフォード大学ソーシャルメディアラボとBetterUp Labsの研究者たちが2025年9月に発表した論文で定義された概念だ。
彼らによれば、ワークスロップとは「良い仕事に見せかけているが、実際には与えられた課題を前進させることのない、AI生成の作業成果物」を指す。
このような概念が生まれた背景には、職場でのAI導入が進んでいながら、それが具体的な生産性の向上には結びついていないように見える現状がある。
AIツールによる成果物が同僚の負担を増やしている?
たとえば、アクセンチュアの調査によれば、業務を「AI主導のプロセス」へと進化させた企業の数は、2023年から24年にかけて倍増した。またギャラップの調査では、職場でのAI使用が2023年の21%から、2024年には40%へとこちらもほぼ倍増している。
さらに、スタンフォード大学が2025年に発表した調査でも、2024年には企業の78%が少なくとも一つの業務機能でAIを使用していると報告しており、これは2023年の55%から大幅に増加している。
ところが、MITメディアラボのNANDAプロジェクトによる2025年7月のレポートによれば、企業の実に95%が、生成AIへの投資に対して測定可能なリターンを全く得られていないという。
またマッキンゼーの調査によれば、92%の企業が今後3年間でAI投資を増やす計画を持っているものの、AIが完全にワークフローに統合され、実質的なビジネス成果を生み出している「成熟した」企業だと自社を評価するリーダーはわずか1%にすぎない。
NANDAプロジェクトの調査では、企業全体では300億ドルから400億ドル(日本円で約4兆5000億円から6兆円)もの巨額の資金が生成AIに投資されているとの結果が示されている。これだけのお金が動いているにもかかわらず、実際にビジネス上の価値を生み出している企業は、100社に5社程度である可能性があるわけだ。
こうした矛盾が生じている理由について、前述のスタンフォード大学の研究者らは、「従業員がAIツールを使って、労力をかけずにまずまずの成果物を作成することが、結果として同僚たちの負担を増やしている(成果物を受け取った人々に、やり直しや修正作業といった余計な負荷をかけている)のではないか」という仮説を立て、それに「ワークスロップ」という名前を付けたのである。
仕事の6分の1が価値を持たないワークスロップの可能性
彼らはこの仮説を検証するため、2025年8月から9月にかけて、米国企業で働く1150人のデスクワーカーを対象に、ワークスロップに関する経験を尋ねた。その結果は衝撃的で、回答者の40%が、過去1カ月間に同僚からワークスロップを受け取ったと答えている。
さらに、同僚から受け取る仕事全体の15.4%が、ワークスロップの基準を満たすという。つまり職場で流通している仕事の約6分の1が、実質的な価値を持たないAI生成物かもしれないというわけだ。
その修正にかけられる時間も無視できない長さだ。
ワークスロップを受け取った1件あたり、平均約2時間が内容の解読・修正に費やされているという結果が出ている。この時間コストを賃金ベースで換算すると、1人あたり月額186ドルに相当するという。また従業員数1万人規模の組織では、年間で900万ドル超に相当する生産性ロスが生じ得るという推計もなされている。
調査では心理的な影響も確認されている。
ワークスロップを受け取った際、それを「不快だと感じた」という回答が過半数を超え、「侮辱的だと感じた」と答えた人も一定割合存在していた。またワークスロップを送った相手に対する評価が下がる傾向も観察されており、相手を「信頼性が低い」と見なすと答えた回答者は約42%、「能力が劣る」と見なしたのは約37%となっている。
興味深いことに、調査によれば、ワークスロップの40%は同僚間で共有されているという。これは「同僚ならAI生成物の内容をチェックしなくてもいいか」といった心理が働いている結果かもしれない。ただ18%は部下から上司へと送られ、16%は逆に上司や上級リーダーから部下へと送られているという。
ではなぜ、こうしたワークスロップがはびこるようになっているのか。そこには現在のAIツールが抱える技術的な限界がある。
ワークスロップをどう乗り越えるか
MIT NANDAレポートによれば、経営者たちが生成AIベンダーを選択する際に重視する要素として、「時間とともに改善する能力」を66%が、「文脈を保持する能力」を63%が挙げている。こうした点が重視される理由は、冒頭で挙げたたとえ話を思い出していただければ明らかだろう。
たとえば、ある弁護士が契約書の下書きをAIに作らせたとしよう。最初は便利に使えるかもしれないが、AIは過去の修正を覚えていない。顧客の好みを理解することもない。前回指摘したミスを、また同じように繰り返す。その結果、毎回、大量の説明を入力し直さなければならない。
実際、MIT NANDAレポートに収録されたインタビューで、ある中堅企業の法律顧問は「最初の下書きには優れているが、クライアントの好みや過去の編集から学ばない」と指摘し、「時間をかけて知識を蓄積し改善していくシステムが必要」だと答えている。
そうした「学習能力」、つまりフィードバックから学び、文脈を記憶し、時間とともに改善する機能が、現在のAIシステムの多くに欠けているわけである。
まさに現時点でのAIは、「いくら指導しても成長しない部下」といったところだ。しかもたちの悪いことに、彼らが作る成果物は表面的には完成度が高く、そのまま顧客や経営層に提出しても問題ないように思える。ところが詳しく見ていくと、そこにはいくつもの間違いがあり、それを見つけて修正するために多くの労力が必要になるのだ。
では、ワークスロップ問題をどう乗り越えれば良いのだろうか。
スタンフォード大学ソーシャルメディアラボの創設ディレクターであるジェフリー・ハンコック教授は、「ワークスロップを減らすのは、『タスクの質へのチームとしてのコミットメント』だ」と提言している。
具体的には、職場でのチームがAIをどのように使用するか、そしてどのような用途が最も適しているかについて、お互いに話し合い、批評する時間を取るべきだという。
また、MIT NANDAレポートでは、AI導入に成功している企業の特徴として、AIツールを「ソフトウェアとして買う」のではなく、「ビジネスサービスとして契約する」という姿勢を持っているという点が挙げられている。
つまり、コンサルティング会社や業務委託先を選ぶときと同じように、成果を基準に評価している。単純なAIの性能や機能の豊富さではなく、「実際にビジネス上の成果を生み出すか」を見ているのだ。
さらに、透明性の重要性も指摘されている。
前述のハンコック教授は、「AIを使用したことを率直に伝えることが重要だ」と述べている。たとえば、時間がなくてAIチャットボットを使ってプレゼンテーション資料を作成した場合でも、それを同僚に伝えることで、相手はどのようなAIやプロンプトが使われたかを理解でき、より建設的な対応が可能になるわけである。
将来的には、前述の高度な「学習能力」がAIに実装されることが標準的になるだろう。そうなれば、AIに「また同じことを言わせるのか!」ということもなくなるはずだ。しかしそれまでは、ワークスロップという問題があることを認識し、職場でどのようなAIを使うのか、それをどう活用するのかを私たち一人ひとりが考えていかなければならない。
小林 啓倫(こばやし・あきひと)
経営コンサルタント。1973年東京都生まれ。獨協大学卒、筑波大学大学院修士課程修了。
システムエンジニアとしてキャリアを積んだ後、米バブソン大学にてMBAを取得。その後コンサルティングファーム、国内ベンチャー企業、大手メーカー等で先端テクノロジーを活用した事業開発に取り組む。著書に『FinTechが変える! 金融×テクノロジーが生み出す新たなビジネス』『ドローン・ビジネスの衝撃』『IoTビジネスモデル革命』(朝日新聞出版)、訳書に『ソーシャル物理学』(草思社)、『データ・アナリティクス3.0』(日経BP)、『情報セキュリティの敗北史』(白揚社)など多数。先端テクノロジーのビジネス活用に関するセミナーも多数手がける。
Twitter: @akihito
Facebook: http://www.facebook.com/akihito.kobayashi