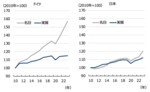消費税減税は高インフレを招く悪手、日本は生産性向上で手詰まり感が漂うドイツを反面教師にすべき
【土田陽介のユーラシアモニター】労働コストとエネルギーコストの引き下げに苦労するドイツの苦境
2025.5.27(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
反EUの右派候補が勝利したポーランド大統領選だが、右派ネット界隈が騒ぐポーランドの右派回帰は本当に起きるか?

あわせてお読みください

大きく毀損されたドルの信用力、基軸通貨ドルの信頼はトランプ政権でどこまで損なわれるか?
【著者に聞く】『基軸通貨 ドルと円のゆくえを問いなおす』の土田陽介が語る、基軸通貨の3条件
長野 光 | 土田 陽介

トランプ関税ショックで改めて問われるロシアの継戦能力、石油・ガス収入が落ち込む中でどこまで突っ張れるか?
【土田陽介のユーラシアモニター】ウクライナとの停戦を視野に入れた直接交渉を呼びかけたプーチン大統領の意図
土田 陽介

超長期金利の上昇は何を意味するのか?円金利の低位安定を支えた二つの「アンカー」に変調の兆し
【唐鎌大輔の為替から見る日本】世界最大の対外純資産国だが、その対外純資産が円転できるとは限らない
唐鎌 大輔

プーチン・ロシアで始まった雇用整理の波、一段と進む戦時経済化で民需と家計所得に大きな打撃か
【土田陽介のユーラシアモニター】労働市場の変調が映し出すロシア戦時経済の綻び
土田 陽介

米国債の格下げでトランプ減税は封じ込められる?「3度目の格下げ」から読み取るべきことは何か
【唐鎌大輔の為替から見る日本】慢性的に進むドルの基軸通貨性の喪失と次に起き得ること
唐鎌 大輔
本日の新着
世界の中の日本 バックナンバー

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治
関 瑶子

「ヒロシマのタブー」避け、硬直化し定型化した語りで「核兵器なき世界」を実現できるのか
宮崎 園子

2026年、重要性増す社会的情動スキルとステージマネジャー猪狩光弘の凄技
伊東 乾

AIのお試し期間は2025年で終了、2026年に顕在化する5つのトレンドとAIで稼ぐ企業・コストになる企業を分ける差
小林 啓倫

子供の能力を伸ばす「非認知能力」教育の誤解と正解
伊東 乾

反ムスリム土葬墓論はなぜ間違っているのか?そもそも神道は土葬が前提、土葬が公衆衛生上良くないという論法も乱暴
鵜飼 秀徳