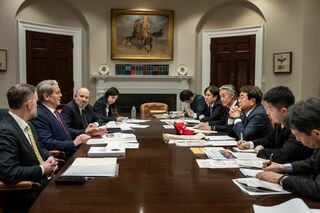トランプ政権はドルの信用力に打撃を与えている(写真:Yagoda.M/shutterstock)
トランプ政権はドルの信用力に打撃を与えている(写真:Yagoda.M/shutterstock)
5月16日、米格付け会社のムーディーズ・レーティングスが、米国債の長期信用格付けのランクを「Aaa」から「Aa1」に引き下げ、この影響から円買い・ドル売りの動きが見られた。関税を中心としたトランプ的経済外交は、ドルの信頼にいかに響くのか。『基軸通貨 ドルと円のゆくえを問いなおす』(筑摩選書)を上梓した三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部副主任研究員でエコノミストの土田陽介氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)
──「基軸通貨としての米ドルに対する議論に、危ういものが多いと感じた」と、本書の執筆動機について書かれています。
土田陽介氏(以下、土田):日本は何かあると円が高くなり、それが輸出の負荷となって景気が悪くなることが多いので、これまで円高に対する警戒感が議論されてきました。
ただ、パンデミック以降は、1ドル110円程度だったドル円レートが、一気に150円台をつけ、振幅を経て160円台になるなど、急速な円安が進みました。このような円安がなぜ生じたのか。これは裏を返すと「基軸通貨のドルがなぜ強いのか」という問題意識につながります。
また、ロシアがウクライナに侵攻したことで、新興国を中心に、世界的なドル離れが起きているとされています。そのことに対して、自分なりに答えを出したいという思いもありました。
──ドルを頂点とした国際金融体制が揺らぐのでは、という見方もありましたね。
土田:その部分に対する問題意識もありました。
アメリカとヨーロッパは経済制裁の一環で、基軸通貨であるドルと、これに次ぐ準備通貨であるユーロの利用をロシアに対して禁止しました。
その結果、ロシアはドルやユーロが使えなくなりますから、人民元、金、ロシア自らの通貨であるルーブル、貿易先のインドのルピーなど、それ以外の通貨をロシアは使わなければならなくなりました。
「これで米ドルを頂点とする国際金融体制が変わっていく」と考える人が、特にネットを中心に一定数見られました。ドルが国際金融通貨の頂点にい続ける状況が未来永劫続くとは思いませんが、反米主義的で感情的な主張を目にして、もう少し冷静に、ドルの強さと基軸通貨とは何なのかをこの際考えてみたいと思いました。
──基軸通貨の3つの条件について説明されています。