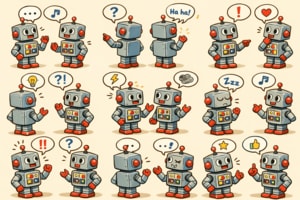銃乱射事件で殺されたウジ君が語り出す……AIで復活した故人を社会活動に参加させることはどこまで許されるか
【生成AI事件簿】再生ボタンを押すと語り出す事件・事故の被害者
小林 啓倫
経営コンサルタント
2024.10.24(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
診察記録の音声テキスト化で起きた生成AIのあり得ない捏造、死を招く「ハルシネーション」をどう防ぐ?