「お前は二度と使わない」伝説の名監督と親子鷹で甲子園を目指したスラッガーの挫折
【ドラフト直前ルポ】知徳高校・初鹿文彦監督と家族の物語(2)
2024.10.20(日)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
親子鷹で甲子園、選手では果たせなかった夢をコーチで実現させた文彦の原点

あわせてお読みください

【見たことのない投球フォーム】東都の雄、亜細亜大に現れた左投げのアンダースロー投手・安井勇有心の希少性
球速は120km台だが、見たことのない球筋で打者を幻惑
矢崎 良一

親子三代「親子鷹」とMAX152kmのドラフト候補、静岡の無名高・知徳高校で起きている現在進行形の奇跡
【ドラフト直前ルポ】知徳高校・初鹿文彦監督と家族の物語(1)
矢崎 良一

正捕手になって気づいた勝ち負けを背負う重圧、控えの2番手キャッチャーだった男がチャンスをつかめた理由
プロを目指さなかった男たち(3)日本通運・鈴木健司コーチの逆転野球人生②
矢崎 良一

身長164cmの「小さなエース」が辿り着いた小さくても、遅くても勝てる投手の境地
プロを目指さなかった男たち(2)鷺宮製作所・野口亮太投手が追い求めた球速140kmより大切なもの
矢崎 良一

甲子園でもプロ野球でもない、社会人野球に憧れたドラフト候補の元・東大野球部主将の生き方
プロを目指さなかった男たち(1)明治安田・松岡泰希捕手が目指した「大人の真剣な野球」
矢崎 良一
本日の新着

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常
【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】
若月 澪子

歯の治療費250万、孫へ贈与が500万…退職金が「蒸発」し、年金が「枯渇」する恐怖
「そこそこの貯蓄」があっても安心できない、年金生活者を襲う想定外の出費
森田 聡子

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力
身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点
市ノ瀬 雅人
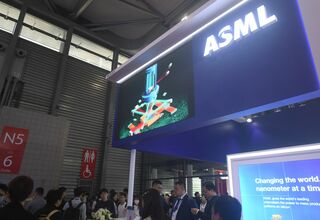
「中国が『EUV露光装置』試作機完成」の衝撃…世界の半導体秩序は抜本的に書き換えられてしまうのか?
莫大なカネとヒトをつぎ込んだファーウェイ、中国半導体版「マンハッタン計画」の行方
湯之上 隆
スポーツの見方・勝ち方 バックナンバー

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に
広尾 晃

「流れを変えるだけの戦力がなかった」 箱根駅伝、“21年連続シード”を逃した東洋大に何が起きたのか?
酒井 政人
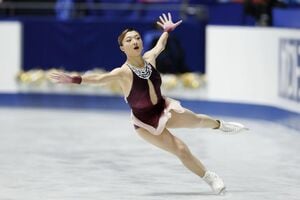
坂本花織の「五輪ラストダンス」、大技なしの女王が築いた“新しい成功モデル”の全貌に迫る
砂田 明子

箱根駅伝V候補が王者・青学大に大きく離された理由とは?全日本1位の駒大はエースが走るも6位、同2位の中大は5位
酒井 政人

なぜ大相撲だけが視聴率20%を取れるのか?WBC・W杯以外は苦戦する地上波スポーツ中継で相撲が勝つ構造的強さ
長山 聡

「来年は優勝しかない」大会新で過去最高の2位の國學院大が見せた強さ、前回11位から3位と大躍進した順大の気概
酒井 政人






