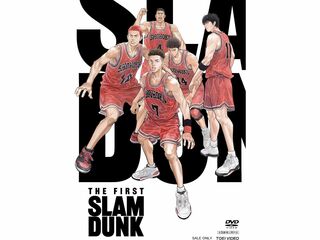元々かかりつけの医師に、1回人間ドックを受けることを強く勧められたことがきっかけだったのだ。
だがかれは結局、診断結果を受け入れざるをえなかった。「何がなんでも新著(『書いてはいけない』……引用者注)を完成させて、世に問いたい」という想いで入院治療を開始した。病室のなかでも仕事をした。
2週間が過ぎると医師の反対を押し切って、「雨が降ろうが槍が降ろうが」と退院した。帰りに焼肉と寿司を食べ、いまでもタバコ(1日5本)を喫っている。やめるつもりもない(『がん闘病日記――お金よりずっと大切なこと』三五館シンシャ、以下同)。
「いつ死んでも悔いのないように生きてきた」
がん宣告されても、驚いたことに、森永氏は恬淡としているのである。
がん宣告は「青天の霹靂」と書いてはいるが、全身から血の気が引いたといった類のことはまったく書いていないのが驚きである。見栄か強がりかやせ我慢かもしれないと思うが、かれは強くて、明るいのである。
多くの人はがん宣告を受けると、「1日でも長い延命を望み、永らえた期間で、旅行に出かけたり、高級なレストランに行ったりする」のだろう。人生は一度だし、「最後は豊かな時間をすごしたい」と思うのはふつうかもしれない。
しかし、と森永氏は、余生を楽しみつくしたいという「欲求はない」と断言している。なぜなら「これまでの人生で、やりたいことは、すべてそのときにやってきたからだ」。だから、自分には「夢」がないと。
同書には最新の治療法や治療費についても詳しく書かれているが、わたしが興味あるのは森永氏の、大げさにいえば死生観である。
森永卓郎氏は「いつ死んでもいいとは思っていない」が、「延命にはこだわっていない」といっている。というのも「いつ死んでも悔いのないように生きてきたし、いまもそうして生きているから」だという。
見上げた覚悟である。しかし凡人は、とてもこういうわけにはいかない。
一般的には、在原業平の「つひにゆく道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」か、大田南畝(=蜀山人)の辞世の歌と伝わる「今までは人のことだと思ふたに 俺が死ぬとはこいつはたまらん」あたりが、われわれの本音に近いのではないか。
わたしはたぶん、がん宣告一発で、ヘナヘナとなってしまうにちがいない。仕事なんかどうでもいいではないか。
『そろそろ家に帰ろう』と言われ、すぐに帰る気分
森永氏がこの本で伝えたかったことは、「人生でやり残したことがほとんどないということだ」といっている。
森永氏は、どう死ぬか、なんか問題ではないといっているようである。むしろ、人間、どう生きたかが問題なのだ。その意味では「これまでの仕事で遊んで、遊んで、遊びつくして、やりたいことはすべてやってきた」。
だからもうこの世にはなんの未練はない、というのだろう。ビートたけしもおなじようなことをいう。そのようなことが可能かどうか知らないが、本人がそういうのだから、そうですかというしかない。
ただ、このあとの氏の言葉がいいのである。
「だから、朝から晩まで、泥んこになって遊んだ子どもと一緒で、十分満たされて、『そろそろ家に帰ろう』と言われたら、すぐに家路につく気分なのだ」
どうですか。森永氏は恬淡として、どこまでも明るくて強いのである。
わたしたちは、到底こんなふうに達観できるとはおもえない。どのようにしたらそういう境地になれるのかと問うても、秘訣はない。
けれど死について不安に思ったり、恐怖を感じたりすることはないのかもしれない。さまざまな想いが生じるだろうが、それもそこまでである。それ以上考えても、しかたがない。行き止まりだし、正解はない。
ふつうに生きていれば、穏やかな死が「家路」に導いてくれるはずである。案ずることはない。その途中で迷子になったものは、古今東西、一人もいないのだから。