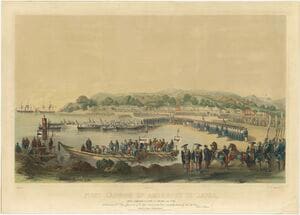逃亡生活から一転、一橋慶喜に仕官
1840年、現在の埼玉県深谷市に生まれる。生家は農業のほか、藍染め原料の加工・販売を営んでいた。それらの染め物材料を江戸ではなく織物産地に直接卸すことで、村内
残り3666文字
1840年、現在の埼玉県深谷市に生まれる。生家は農業のほか、藍染め原料の加工・販売を営んでいた。それらの染め物材料を江戸ではなく織物産地に直接卸すことで、村内
残り3666文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら