「日本資本主義」を作った男・渋沢栄一、実業界引退後に築いたもうひとつの豊穣な人生
【新連載】「あの人」の引き際――先人はそのとき何を思ったか
2024.6.25(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

新一万円札の顔、渋沢栄一がとてつもない“鉄道人”だった「意外な足跡」
45以上の鉄道会社立ち上げに関与、並々ならぬ執念で鉄道建設を推進した理由
小川 裕夫

平安貴族の年収は?10年間無官だった紫式部の父・藤原為時はどう生活していたのか?
書籍『平安貴族列伝』発売記念!著者・倉本一宏氏に聞く平安時代のリアル(3)
倉本 一宏

本能寺の変、死を覚悟した信長がとった最期の行動
織田信長「遺体」の行方は? 戦国時代の謎と真実に迫る【JBpressセレクション】
小和田 泰経

武田信玄はなぜ息子を「殺した」のか?
戦国の雄・武田氏滅亡の理由とは。戦国時代の謎と真実に迫る
小和田 泰経

定年後に楽しい人生を送る人、惨めに過ごす人
第91回 過去の成功体験を捨てリスタートする覚悟を持てるか
藤田 耕司
豊かに生きる バックナンバー

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
髙城 千昭
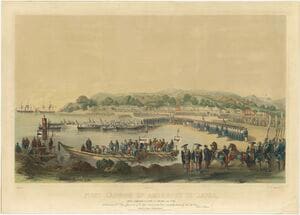
哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化
鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義
川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性
川岸 徹



