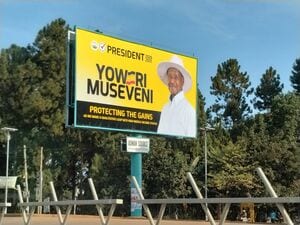国際裁判所に深く関わる日本
20世紀に入り、第1次世界大戦後の国際連盟発足に伴って、「常設国際司法裁判所」が設立されます。多くの犠牲者と多大な破壊を招いた大戦の惨禍を教訓に、紛争が起きてから裁判の形を整えるのではなく、裁判所をオランダのハーグに設置して、裁判官もあらかじめ決めておくというものでした。
このかたちをほぼ引き継いだのが、第2次世界大戦後に国連にできた現在のICJです。国連憲章94条は加盟国に対し、自国が当事者となった事件についてICJの裁判に従うことを義務付けています。
ただ、世界の紛争は冷戦終結後の1990年ごろから様変わりしました。それまでは国際法違反に対して国家の責任を問えば済んでいました。しかし旧ユーゴスラビア内戦などでは国家が統治能力を失って無政府状態に陥るなかで、人道に対する犯罪が発生したのです。
国際人道法に反するような重大な違反を行った個人の責任を問うべきだという機運が高まり、国内裁判所を補完する形で設立されたのがICCです。設立に向けて議論を重ねたのは国連でしたが、ICCは国連の一部ではなく、独立した機関です。
それまで個人の戦争犯罪を裁いた例としては、第2次世界大戦の戦犯を裁くドイツのニュルンベルク裁判や東京裁判、1990年代の旧ユーゴやルワンダの内戦に関する国際戦犯法廷があります。これらはいずれも特定の事例に対する臨時的な法廷で、常設のICCとは区別されます。
 今年3月にICC所長に就任した赤根智子氏(写真:共同通信社)
今年3月にICC所長に就任した赤根智子氏(写真:共同通信社)
こうした国際裁判所に日本は深く関わってきました。外交官で国際法学者の安達峰一郎氏(1869〜1934年)はICJの前身である常設国際司法裁判所の発足から関わり、後に所長も務めました。日本はこれまでICJに4人、ICCに3人の裁判官を輩出しています。日本は現在ICCで最大の分担金拠出国で、現在の所長は日本で長く検事を務めた赤根智子氏です。