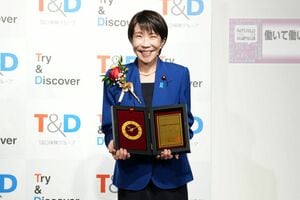「年収の壁」は働き手にとっても職場側にとっても悩ましい存在になっている(写真:mapo_japan/Shutterstock)
「年収の壁」は働き手にとっても職場側にとっても悩ましい存在になっている(写真:mapo_japan/Shutterstock)
(川上 敬太郎:ワークスタイル研究家)
そもそも「年収の壁」とは何か?
パートで働いている人が多い職場では、年末が近づくと「年収の上限を超えそうだから、扶養枠から外れないようシフト調整しないと」などと“年収の壁”対策に関する話題が出てきます。
年収の壁とは、扶養から外れる条件となる収入上限のことです。もう少し働いて収入を増やしたいと考えている人にとって、年収の壁は悩みのタネになっています。また、年末が近づくにつれてシフト調整の手間が増えたり、空いた穴を埋める人手を確保しなければならないなど、職場側にとっても悩ましい存在です。
政府はそのような悩みを解消するため、年金制度改革を予定している2025年までの暫定措置として「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。一定の条件を満たせば、年収上限を超えても社会保険の扶養にとどまることを可能とする施策です。
ただ、それほどに問題視されている年収の壁なのに、その姿を正確に把握するとなると一筋縄ではいきません。そのため、「とりあえず103万円を目安にしておけば大丈夫だろう」などとザックリした判断をしがちです。
年収の壁という言葉自体はよく耳にするのに、なぜ妖怪変化のごとく、その正体はつかみづらいのでしょうか。
年収の壁が分かりづらい理由には、大きく3点あります。1つは、種類がいくつもあることです。年収の壁には大きく4つの種類があります。「住民税」「所得税」「社会保険」「家族手当」です。
住民税は、市区町村や都道府県によって提供されるサービスのための税金。所得税は、個人の所得に対してかかる税金。社会保険は税金ではなく文字通り保険です。健康保険と年金保険のことを指します。
一方、家族手当とは自分の収入ではなく、配偶者が勤める会社から配偶者自身に対して支給されるものです。配偶者手当とか扶養手当などと呼ばれることもあり、会社によって名称は異なります。また、家族手当が支給されない会社もありますし、支給額も月に数千円から数万円とまちまちです。
年収の壁とはこれら4種類の総称であり、そのことが正体を把握しづらくさせています。