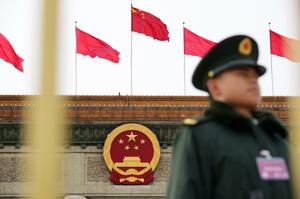ワヤンは2003年にユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、まさにインドネシアを代表する伝統文化であるが、一貫して一般庶民に近い芸能でもある。例えば1960年代には、宣教師が、地元住民にキリスト教を布教するために、イエス・キリストやマリア様をかたどった人形を作り、オリジナルの演劇を作ったという記録がある。オランダそして日本の植民地時代には、反植民地抵抗運動の活動家が地元住民の間に独立機運を醸成する目的でワヤンを利用したという。
最近では、ワヤンと現代アートを組み合わせたパフォーマンスを行う団体もある。インドネシア人にとって、ワヤンは娯楽であり、教育であり、そして思想だ。
「Momotaro project」の経験を通じて、筆者にとって芸術とは、もはや遠くから鑑賞するものではなくなっていた。不器用ながら自分の手で触れて、関わり、そして、創作の一部になることだった。ワヤンで日本の物語を演じることができれば、面白いのではないか。特に、桃太郎であれば既にインドネシア語版も手元にあるし、絵画でできるならばワヤンでもできるのではないか。
こうして、展覧会の絵もまだ完成していない2022年12月にMomotaro Wayangプロジェクトを発足させてしまった。
ただ、実際にはそう簡単ではない。絵画に比べて、関係者が増えるからだ。ワヤンの構成要素は大きく分けて3つある。1つ目は人形。2つ目は、ガムラン。そして、3つ目が人形遣い(ダラン)である。
 一般的な人形の製造工程(筆者提供)
一般的な人形の製造工程(筆者提供)
1つ目の人形作りは、牛皮(違う材料のものもある)を薄く延ばしたものに下絵を施し、そして色付けを行う。筆者も工房を訪問し、制作現場を見学する機会を得たが、職人による細かな線使いや彩色に魅了された。
2つ目のガムランは、インドネシアのオーケストラと呼べるもので、金属製、木製、竹製の打楽器を用いて合奏する民俗音楽である。独特の旋律やボーンという音に馴染みのある方もいるかもしれない。
そして、3つ目の人形遣いこそが、個人的にはワヤンにおいて最も重要だと考える。一般的なワヤンは、この人形遣いが全体を支配し、ある意味で、指揮者兼歌手とも言える。時には即興で愉快なジョークを飛ばし、時には悲しげな口調で観客の涙を誘う。
インドネシアではワヤンの演目はマハーバーラタやラーマヤナを使用することが多いが、前述のとおり、必ずしもこれらの物語に限らないのがインドネシアの文化の懐の深さである。筆者はインドネシアを数回訪れて、日本人とインドネシア人の感覚は意外と近いのではないかと感じた。例えば、インドネシア国民の90%はイスラム教徒でありながら、クリスマスも盛大に祝う。そもそも、マハーバーラタやラーマヤナはインドのヒンドゥー教の物語だ。一本筋を通しながらも様々な文化を受け入れる姿は、日本を見ているようである。
◎新潮社フォーサイトの関連記事
・少し出遅れた慎重派も必読――新NISAで最後に笑うのは誰? 投資信託に向く人、向かない人
・「上にモノを言う」べきダイハツ新経営陣が早くも失望される理由
・日本発売、肥満症治療薬「ウゴービ」の「効果と注意点」「そもそも手に入るのか」