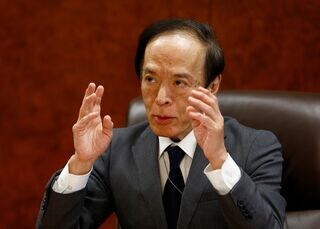(写真:g0d4ather/Shutterstock.com)
(写真:g0d4ather/Shutterstock.com)
米国の金融引き締め長期化観測や、イスラエルとパレスチナの戦闘拡大など、世界経済に波乱要因が台頭している。そんな中、先進国で唯一、緩和的な金融政策を続ける日本銀行の動向が注目されている。7月にイールドカーブ・コントロールの弾力化に踏み出した植田和男総裁は今後、いつ、どのような手を打つのか。次の論点について、元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説する。(JBpress編集部)
(神津 多可思:日本証券アナリスト協会専務理事)
現在のインフレ圧力はすぐには収まらない
日本銀行の「異次元緩和」は、ホームページでは「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」と表現されており、さらにそれは①イールドカーブ・コントロール、②オーバーシュート型コミットメント、の2つの要素から成り立つと整理されている。
要するに、短期金利、長期金利の両方を様々な資産を大量に購入することによってコントロールし、かつそのような金融政策を消費者物価の上昇率が安定的に2%を超えるまで継続するというのが「異次元緩和」の要因分解ということになる。
このうち、これからの金融政策において本質的な論点となるのは短期金利のコントロールだろう。というのも、長期金利については、7月の金融政策決定会合で日本銀行が決定したイールドカーブ・コントロールの弾力化により、実質的に市場実勢追随型に変わってしまったと考えられるからだ。
また、オーバーシュート型コミットメントについては、2022年4月以降、最近に至るまで、消費者物価総合の前年比は一貫して2%を上回っており、すでに十分オーバーシュートしていると言える。
その短期金利についても、マイナス金利は、9月の本コラム「マイナス金利政策の解除は十分に現実的な選択肢、日銀が動くべき時が来ている」で議論したように、すでに内生的な物価押し上げ効果を失っていると考えられる。したがって、2%のインフレ目標を前提に、今後、短期の政策金利を、ゼロを超えてどう動かしていくかという流れこそが重要なのではないだろうか。
7月の日本銀行の政策変更については、8月の本コラム「『量』から『金利』へ動く日銀、YCC修正に続き必要な金融政策を整理する」で論じた通り、ほとんど公表文を変えないままに、10年物国債金利の指値オペの水準が市場実勢に合わせ引き上げられた。金融市場もそれを受け入れ、長期債市場でも大きな混乱はなかった。
【関連記事】
◎マイナス金利政策の解除は十分に現実的な選択肢、日銀が動くべき時が来ている
◎「量」から「金利」へ動く日銀、YCC修正に続き必要な金融政策を整理する
現在のインフレ圧力は、グローバルにみてもすぐには収まらないとの見方がこのところさらに強まっているようで、米国の長期金利は一段高となっている。要するに、先行きの経済の見通しがより不透明化したことで、長短金利差、すなわち「ターム・プレミアム」が広がっているということだ。