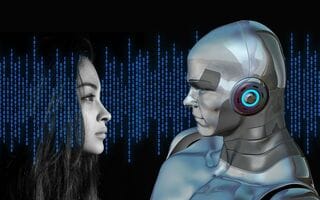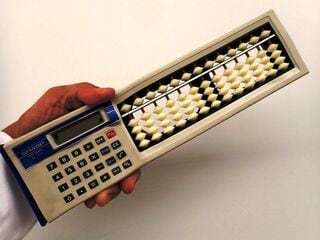世界トップレベルの研究機関育成、その候補に東大が落選した理由
東北大を選定、東大デザインスクール案は世界で通用しなかった
2023.9.8(金)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
画期的改革も登場、日本の未来を左右する2025年大学改革の中身

ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
画期的改革も登場、日本の未来を左右する2025年大学改革の中身