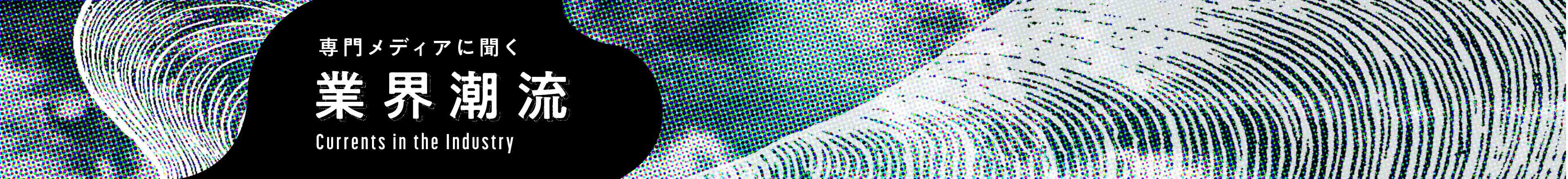写真提供:共同通信社
写真提供:共同通信社
少子超高齢社会に突入し、先細る個人消費。百貨店、総合スーパー、食品スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、EC(電子商取引)と、さまざまな業態が入り乱れてサバイバル競争と合従連衡を繰り返す小売・流通業界の未来はどうなるのか。
高度経済成長期から日本の小売・流通業界の移り変わりを見つめ続けてきた月刊『激流』。現編集長の加藤大樹氏に話を聞いた。
<連載ラインアップ>
■第1回 「一気にドラッグストア大再編が進む可能性も」月刊『激流』編集長に聞く小売業界の注目動向(本稿)
■第2回 総合スーパーの再編は最終ステージに突入? 月刊『激流』編集長に聞くGMS再編・改革の最前線
■第3回 セブン、ファミマ、ローソン…月刊『激流』編集長に聞くコンビニ業界「成長持続」のための打ち手
<フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本ページの右上にあるフォローボタンから、シリーズ「専門メディアに聞く 業界潮流」をフォローできます。
●フォローしたシリーズの記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
新型コロナウイルス禍が業界の一大転換点に
――加藤さんが編集長を務める月刊『激流』の取材領域、編集方針などについて教えてください。
加藤大樹氏(以下・敬称略) 月刊『激流』は1976年創刊の流通業界専門誌で、今年、48年目を踏み出したところです。
取材領域は小売業界全般です。百貨店から総合スーパー、食品スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、EC(電子商取引)、そしてユニクロのような専門店です。主な読者は小売業界の経営幹部、卸売業界、メーカーの方々なので、人事や出店動向など、経営戦略に関わる部分を中心に取材し、記事をまとめています。
時には業界にとって耳の痛い辛口の記事を載せることもありますが、「読者のためになる視点で記事を作成する」ということを何より大事にしているためです。
――加藤編集長が入社してから、小売業界にとって大きな転換点になったのはどんな出来事ですか。
加藤 私が国際商業出版に入社したのは、ちょうどリーマンショックが起きた2008年です。日本はまさにデフレの真っ只中で、小売業界にとっても非常に厳しい時代でした。
入社後の約15年間で小売業界の全業態に大きな影響を及ぼした出来事といえば、やはり新型コロナウイルス禍です。
以前から言われていたのは、2021年の東京オリンピックが終われば景気が後退し、小売業界もいよいよ真冬の時代に突入するということでした。ところが、即そうした状況にはなりませんでした。新型コロナウイルス禍により、小売業界の差し迫った問題が一時的に解消されたためです。
例えば、人手不足に苦しんでいた食品スーパーでは、閉店が相次いだ外食産業からの人材流入により逼迫(ひっぱく)が和らぎました。そして、新型コロナウイルス禍の中でも、既存店舗への投資や新店舗の展開、省力化のためのデジタル投資を積極的に行った企業では、コロナ禍明けにその効果が売上や利益などの数字に表れています。アフターコロナを見越した経営努力を行った企業と行わなかった企業の差が、ここに来て一気に広がっています。