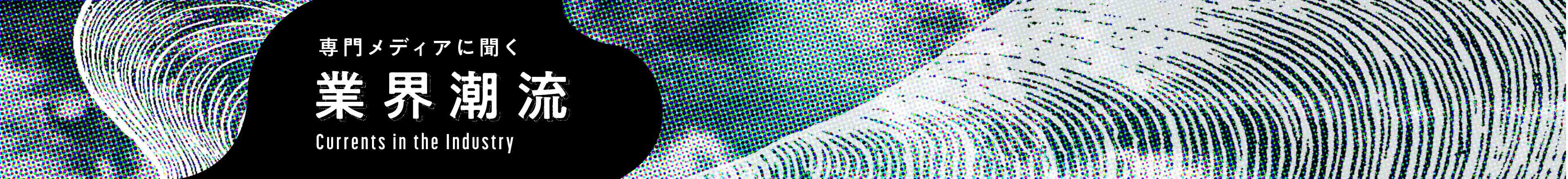写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
写真提供:日刊工業新聞/共同通信イメージズ
総合スーパー(GMS)業界の再編が新たなステージに入った。西友が北海道と九州の店舗をそれぞれイオン北海道とイズミに売却、セブン&アイ・ホールディングスはイトーヨーカ堂の新規株式公開を目指すというニュースが2024年に入って相次いだ。かつては流通産業の花形だったGMSはなぜ苦境に立たされ、どう生き残ろうとしているのか。
流通業界の専門誌、月刊『激流』編集長の加藤大樹氏に話を聞いた。
<連載ラインアップ>
■第1回 「一気にドラッグストア大再編が進む可能性も」月刊『激流』編集長に聞く小売業界の注目動向
■第2回 総合スーパーの再編は最終ステージに突入? 月刊『激流』編集長に聞くGMS再編・改革の最前線(本稿)
■第3回 セブン、ファミマ、ローソン…月刊『激流』編集長に聞くコンビニ業界「成長持続」のための打ち手
<フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本ページの右上にあるフォローボタンから、シリーズ「専門メディアに聞く 業界潮流」をフォローできます。
●フォローしたシリーズの記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
ヨーカドーは首都圏にフォーカス
――今年、西友が北海道の店舗をイオン北海道に、九州の店舗をイズミに売却しました。これによりGMS業界の再編は新たなステージに入ったと言われています。
 【月刊激流】
【月刊激流】1976年、製配販にまたがる流通業界の専門誌として創刊。スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、百貨店など、小売業の経営戦略を中心に、流通業の今を徹底的に深掘り。メーカーや卸業界の動向、またEコマースなどIT分野の最前線も取り上げ、製配販の健全な発展に貢献する情報を届ける。
加藤大樹氏(以下・敬称略) GMS業界では長らくイオンとイトーヨーカ堂が2大勢力でした。しかし、イトーヨーカ堂はすでに北海道、東北、信越からの撤退を発表していて、今後は基本的に首都圏にフォーカスし、業態もGMSではなく食品スーパー(SM)業態を軸に展開していく方針です。
一方のイオンは依然としてGMSを屋台骨と捉えており、規模拡大に積極的です。北海道の西友店舗を買収したのもその一環ですし、今後、もし西友が本州の店舗も売りに出すとしたら、その買い手はイオンしか考えられないと言われています。
仮にイオンが本州の西友も手に入れたら、GMS業界では圧倒的な勢力となります。そういう意味でかつては全国展開していたイトーヨーカ堂が地方から撤退し、北海道の西友がイオン傘下に入ったことは、とても大きな意味があります。
――西友は本州の店舗も売却する可能性があるのですか。
加藤 現在、西友の大株主はKKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)という投資ファンドです。投資ファンドですから当然、出口戦略を考えているはずです。もちろん出口戦略の中には上場という選択肢もあるかもしれませんし、報道によれば北海道と九州からの撤退はKKRが判断したことで、西友自身は本州・首都圏に経営資源を集中させると言っているようです。しかし、業界関係者とこの話をすると、いずれ本州の店舗も売却するだろうという見方の方が少なくありません。
長年の課題だった衣料品と住居余暇関連商品
――地方では百貨店がどんどん減っています。GMSも収益が厳しいところが多いようですが、かつては流通産業の花形だったGMSはどうして苦境に立たされるようになったのでしょうか。
加藤 GMSが消費者から支持されたのは、衣食住に関わる商品がワンストップで買えて便利だったからです。けれどもユニクロやニトリなど、カテゴリーキラーと呼ばれる専門店が台頭し、GMSの商品の魅力が相対的に低下してきました。GMSにとって食品は品ぞろえの柱ですが、実は利幅が薄く、稼ぎ頭は衣料品や住居余暇(住余)関連商品でした。ですからそれが売れなくなると、非常に厳しいわけです。
もちろん背景には少子化や人口減少といった社会的な課題もありましたが、衣料品と住余関連商品はGMSにとって長年の課題になっていたのです。そのためイトーヨーカ堂は、肌着などは別にして、紳士服や婦人服については自分たちで企画し、在庫も自分たちで持って販売するというモデルから撤退する方針を掲げるようになりました。端的に言えばイトーヨーカ堂は、脱GMS路線に舵を切ったわけです。
それに同社の親会社であるセブン&アイ・ホールディングスは、今やコンビニの会社です。コンビニでグローバルに稼いでいくのが成長戦略なのです。実際、セブン&アイ・ホールディングスは、イトーヨーカ堂の株式上場を検討していることも明らかにしています。祖業であるGMS事業をグループから切り離すということです。もちろんイトーヨーカ堂自身も構造改革に取り組み、不採算店は閉めていっています。