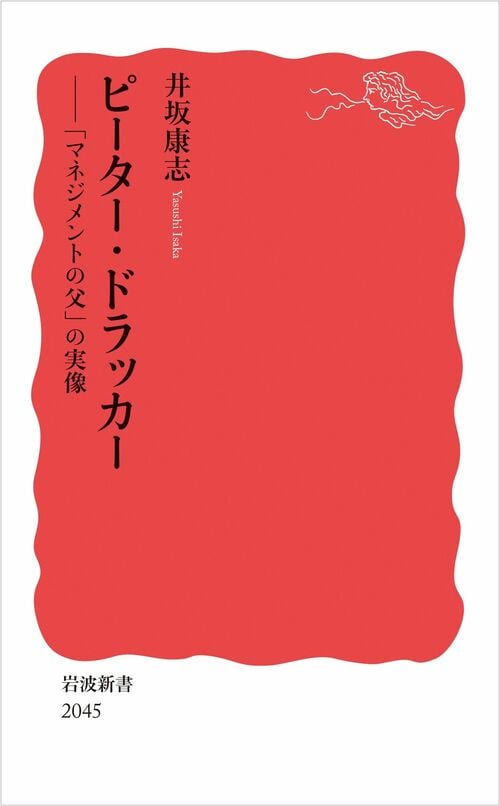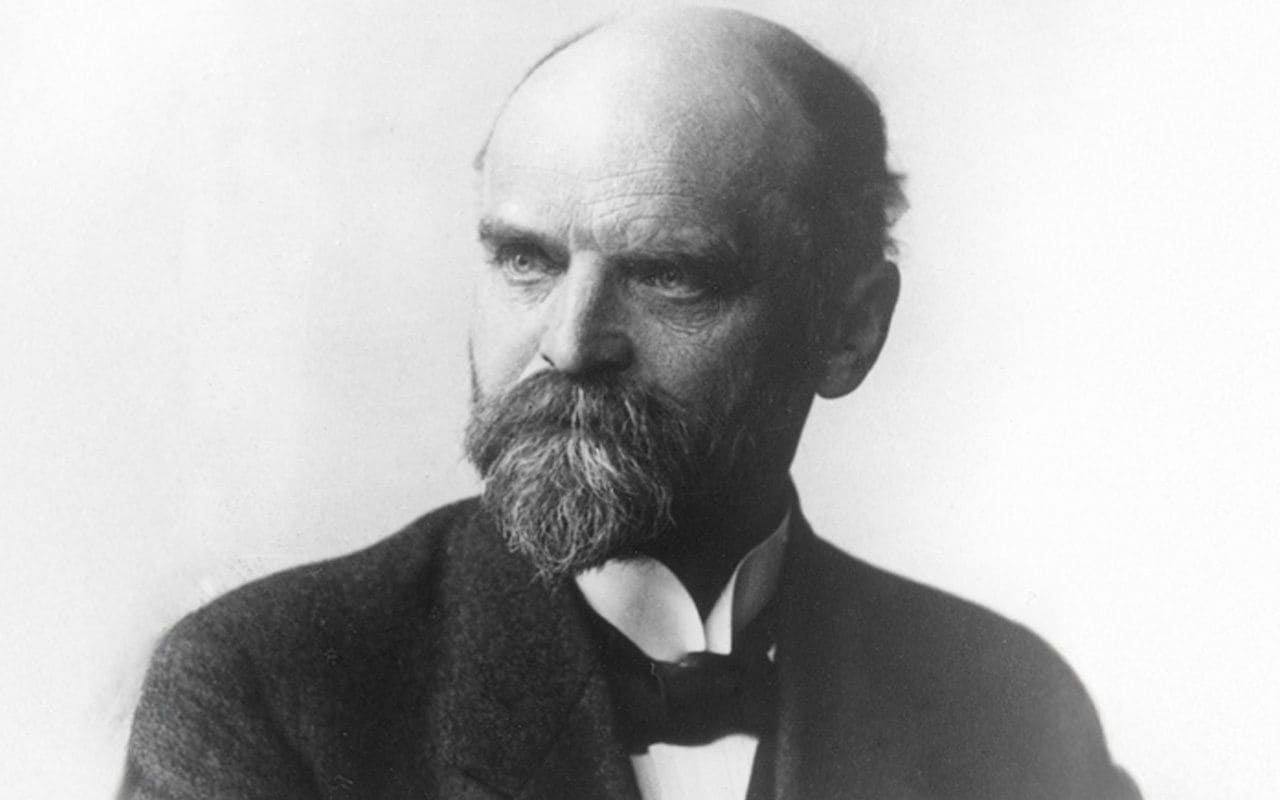 ドイツの社会学者フェルデナンド・テニエス(1855–1936)
ドイツの社会学者フェルデナンド・テニエス(1855–1936)出所:Wikipedia 撮影:Ferdinand Urbahns / public domain
「マネジメントの父」と呼ばれ、日本では1956年発行の『現代の経営』以来、数々のベストセラーを生んだピーター・ドラッカー。日本の産業界に多大な影響を与えたと言われる一方、その人物像が語られることは少ない。本稿では『ピーター・ドラッカー ――「マネジメントの父」の実像』(井坂康志著/岩波新書)から内容の一部を抜粋・再編集。没後20年となる現在も熱心な読者が絶えないドラッカーの人生と哲学、代表的な著書が生まれた背景を紹介する。
働きながら図書館に通って本を読み漁り、人間観や組織観の基礎を培った知られざるドラッカーの青年期とは?
第2節 時代への目覚め
父アドルフはウィーン大学を卒業して身を立てた模範市民のひとりとして、息子にも同様の道を望んだ。一方、ドラッカーには早い時期からインテリ嫌いの傾向が芽生えており、ストレートに大学に進む意志はなかった。進路では譲らず、その決断に父は失望したが、息子の願いを尊重し、最終的には受け入れた。
1927年、ギムナジウムを卒業して、次なる居住地として北部ドイツのハンブルクを彼は選んだ。そこで機械製品の貿易会社の見習いとなった。
勤務のかたわらハンブルク大学法学部に在籍することにしたが、それは父への言い訳に過ぎなかった。誰にも知られていない土地で、好きな本を読み、音楽を堪能できるだろうと彼は考えていた。夢見ていた異郷への出立、自分自身で稼ぎ、心身両面での自立を信じていた。
出発の日、さまざまな社交への気遣いから、父は息子のためにコートと燕尾服(えんびふく)を作らせた。
だが、ドラッカーは実務と研究に没頭して、ほとんど外出することなく、袖を通すのは稀だった。併せて、スペインのイエズス会司祭で人生訓を多く残したバルタザール・グラシアンの書物数冊が手渡された。
自己形成への第一歩を踏み出したのが、彼にとって何より大きな事件だった。生まれる場所を選ぶことはできないが、生きる場所を選ぶことはできる。時代のうねりの中で、彼は故郷を潔(いさぎよ)く捨てた。後の回想によれば、ギムナジウムの同窓28名のうち、ウィーンにとどまったのは4名しかいなかった。