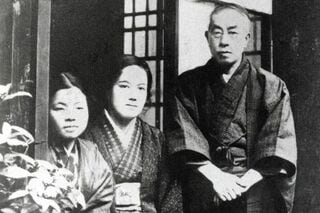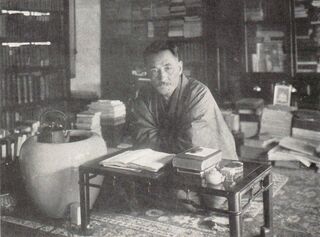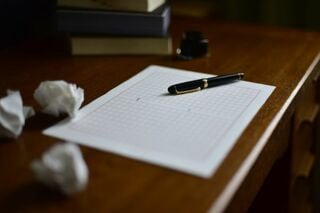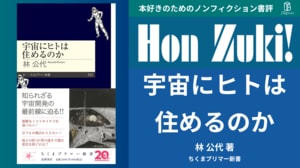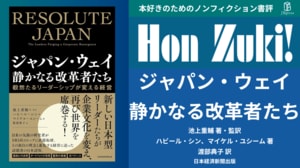大杉栄(左)と伊藤野枝(1923年、写真:共同通信社)
大杉栄(左)と伊藤野枝(1923年、写真:共同通信社)
春から新たな気持ちで、勉強に取り組んでいる――。学生のみならず、そんな社会人も多くいることだろう。中には学習が思うようにいかず、自分にがっかりしてしまっている人もいるかもしれない。しかし、「偉人」と呼ばれた歴史人物たちもまた、勉強には苦労しており、さまざまな葛藤があった。偉人たちはどんなふうに勉強していたのか。
(*)本稿は『ヤバすぎる!偉人の勉強やり方図鑑』(真山知幸著/大和書房)の一部を抜粋・再編集したものです。
周囲の人が逃げ出すほど動物だらけの生活を送る(平岩米吉)
みなさんは、犬や猫などペットを飼っていますか?
平岩米吉は、動物について独自に研究を重ねた「動物学者」です。明治31年に東京亀戸の商家である竹問屋の6男として生まれました。
当初、米吉が夢中になったのは「連珠」(れんじゅ)です。連珠とは、五目並べを改良したゲームのこと。当時、人気を博していましたが、やがてブームは下火に。連珠7段を持つ平岩は、その情熱を動物へと注ぐことになります。
昭和3年に「日本犬保存会」の設立に関わると、翌年には、東京の目黒区自由が丘に家を建て、動物だらけの生活をスタートさせました。のちに、こう振り返っています
「私は9頭のオオカミを飼い、そのうち6頭をすっかり馴らすことができた。彼等はみな、犬のように耳を引き、尾を振り、体をすりつけたり、ころがったりして喜び、時には、鼻声を立てながら私の顔中をなめまわし、感きわまって小水までもらしてしまうほどだった」
こうして9頭のオオカミを飼い始めたことを皮切りに、ジャッカル・タヌキ・ハイエナ・キツネなど、数多くの野生動物を飼った米吉。その臭いのきつさから、隣人が次々と引っ越したとか……。
しかし、平岩はただ飼育しただけではありません。動物たちと寝食をともにして、その行動をつぶさに観察。事細かに記録をとることで、動物への理解を深めていきました。
昭和9年には、『動物文学』を創刊して、自身の研究成果を発表しながら、他の人にも「動物愛」を書いてもらうようになります。本書にも登場する南方熊楠、柳田国男、折口信夫ら著名な書き手を、巻き込んで、雑誌を作り上げました。
さらに翌年には「動物文学会」を設立した平岩。コミュニティを作りながら、自分の「好き」をどんどんと拡散させていったのでした。
 ©しまだなな 『ヤバすぎる!偉人の勉強やり方図鑑』より
©しまだなな 『ヤバすぎる!偉人の勉強やり方図鑑』より
【こぼれ話】
動物愛がハンパなかった平岩米吉は、なんとオオカミを連れて銀座まで散歩に出かけたことがあるとか。デパートの屋上まで連れて行くも、誰もまさかオオカミだとは思わなかったそうです。
動物好きといえば、西郷隆盛も愛犬トラを溺愛して、どこにでも連れて行きました。ほかの人たちが芸者に酌をさせるなか、西郷はトラを引き連れてやってきると「犬にウナギを出してやってくれ」と言ったそうです。
動物好きで行動が読めない……そんなところは、二人の共通点だといえそうです。
【名言】
「いかにむずかしい事柄でも、これを平易に簡潔に表現するのが本当である」