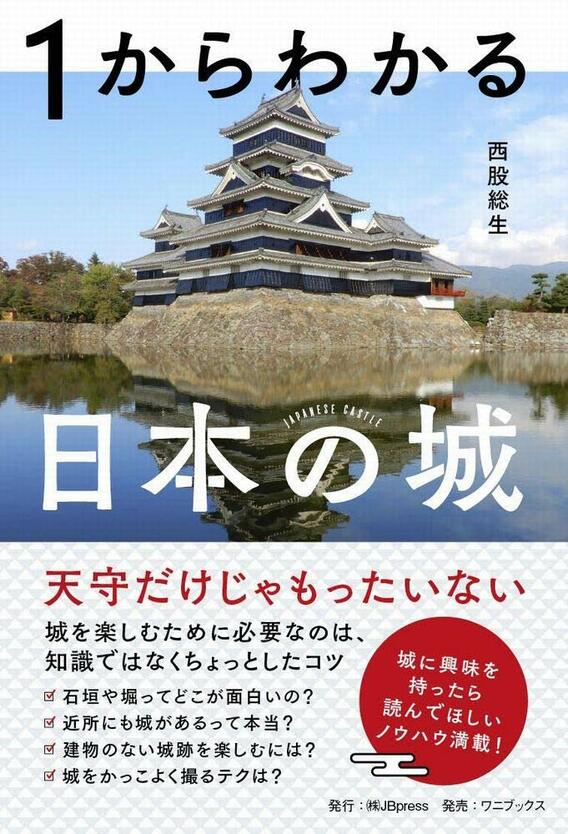本当に「美しい」天守なのか?
城の本の多くは、この天守を美しい、と評する。けれども、大天守を西側の真正面からよく見てほしい。城の天守は下層階から上層階へと小さくなってゆく。この比率を「逓減率(ていげんりつ)」というが、松本城の大天守は逓減率がガタガタである。
 写真2:西側正面から見た大天守。軒の出はバラバラ、逓減率もガタガタである
写真2:西側正面から見た大天守。軒の出はバラバラ、逓減率もガタガタである
 写真3:姫路城天守。比べてみると松本城の不格好さは一目瞭然。姫路城大天守もよく見ると左右非対称なのだが不格好さは感じない
写真3:姫路城天守。比べてみると松本城の不格好さは一目瞭然。姫路城大天守もよく見ると左右非対称なのだが不格好さは感じない
それに、写真2をよ〜く見てほしい。大天守の向かって右側では、一重目と二重目の壁の立ち位置が同じだが、左側では逓減して二重目の壁が内側に入っている。おそらくは、その影響だろうが、左側の屋根が壁の隅にちゃんと納まっていない(写真4)。
 写真4:屋根が壁の隅に納まっていない。こんな不細工な天守は他にない
写真4:屋根が壁の隅に納まっていない。こんな不細工な天守は他にない
また、大天守各階の縦横比や軒の出(軒の深さ)が各階マチマチなので、見る角度によっては四重目が引っ込んで見える。その分、五重目の壁が腰高で頭でっかちな印象を受けてしまうのだ。
 写真5:この角度からだと四重目が五重目より小さく見えて不安定な印象を受ける。破風を付けることで辛うじて不格好さが目立たなくなっている
写真5:この角度からだと四重目が五重目より小さく見えて不安定な印象を受ける。破風を付けることで辛うじて不格好さが目立たなくなっている
はっきりいって、松本城の大天守は不格好な建物である。少なくとも、現存天守でこんな不細工は他にない。それに、多くの人は、天守を見ると松本城を見た気分になって帰ってしまうので気付かないのだが、疑問が生じるのは天守だけではないのだ。
この城で石垣造りになっているのは、本丸と虎口部分だけである。二ノ丸以下は土塁造りで、堀幅も近世城郭としては物足りない。松本城はもともとペッタンコな平城だから、堀が小さく土塁が低く、石垣も一部だけとなれば、難攻不落は期待できないではないか。
 写真6:松本城二ノ丸の土塁と堀。土塁も堀も近世城郭としては並み以下のサイズ
写真6:松本城二ノ丸の土塁と堀。土塁も堀も近世城郭としては並み以下のサイズ
そもそも、天守は城を構成するたくさんのパーツの一つにすぎない。だから、天守があるから名城と評価するのは、本当はおかしい。名城という評価は、石垣・堀・縄張などのトータルから成り立つはずでる。
しかし、「城そのもの」のトータルな評価からするなら、松本城は少なくとも堅城ではない。むしろ凡城と評するのが妥当だろう。
もし、国宝の天守が現存していなかったとしたら、松本城は名城どころか、研究者と一部のマニアの間でしか知られない、凡百の城の一つにすぎなかったはずである。(続く)
 写真7:もし天守がなかったとしたら、松本城の人気は小諸城や上田城に遠く及ばなかっただろう
写真7:もし天守がなかったとしたら、松本城の人気は小諸城や上田城に遠く及ばなかっただろう
[お知らせ]9月15日(金)〜18日(月祝)の4日間、横浜の鶴見サルビアホールにて、お城好きによるお城好きのためのイベント「城熱祭」が開催されます。西股は17日、城郭写真家の畑中和久さんとのトークセッション「城とカメラの深イイ話」などに登場予定。詳しくは城熱祭実行委員会のホームページへ。