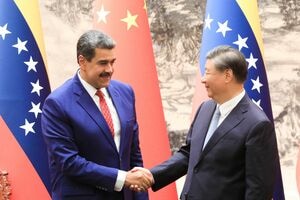そこで日本がひとつの役割を果たす。1960年に現在の新日米安全保障条約を結ぶと、そこに経済協力条項が盛り込まれたことで、日本の高度経済成長がはじまる。日本から生産性の優れた工業製品が大量に輸出されると、米国からは安価な穀物が大量に日本に輸入されるようになった。経済成長は食の西洋化ももたらし、米国から畜産技術が持ち込まれたこともあって、飼料穀物の需要も高まっていく。
この対米貿易構造が日本の高度経済成長の本質であることは言を俟たないが、一方で食料自給率は下がり続け、いまでは40%を割るまでになった。それも言ってしまえば、米国の余剰穀物の捌け口として日本市場が機能した結果だが、米国がなければいまの日本はなかったし、いまでは米国なしに日本の食料供給は成り立たない。そうしていまの日本はG7として対ロシア陣営にいる。
21世紀になっても「食料が武器」の時代は終わらず
さらに歴史をたどれば、東洋の奇跡とも称えられた戦後日本の高度経済成長だが、1980年代に入ると日米の貿易摩擦が顕著となる。そこで米国が貿易赤字を埋めるために、日本にもっと買えと迫ったのが農産物だった。日本に農産物の輸入自由化を求め、日本は91年に牛肉・オレンジの輸入自由化に踏み切る。95年からはコメの輸入もはじまっている。
やがて、高度成長の絶頂だったバブル経済が崩壊してデフレの時代が日本に訪れると、中国に食料を依存するようになった。コストが安い食材、食品を加工して日本に輸入するようになる。だが、そこで浮かび上がったのが、中国の“毒食”問題だった。それがいまでは、中国が日本の農林水産物・食品を放射性物質に塗れた“毒食”の扱いをする。
市場を開けという米国と、市場を閉じる中国との違いはあっても、貿易、外交の取引材料に食料を利用するところは変わらない。
そう考えてみると、歴史は同じことを繰り返しているようだが、世界の転換点では食料が武器としての威力を最大限に発揮する。中露に欧米、それにグローバルサウスを巻き込んだ今後の国際秩序の形成に大きな影響を与える可能性も、無視はできない。