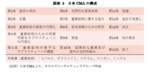日産「リーフ」も外れた米国のEV税額控除、その背景にあるバイデン政権の矛盾
バイデン政権が進めるフレンド・ショアリングと自国優先政策の落としどころ
2023.4.18(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
サプライチェーン上の人権侵害排除に本腰を入れる政府が埋める外堀

あわせてお読みください

貧しくなる世界にIMFが警告、本格化する「スローバリゼーション」の時代とは
サプライチェーンの再構築によって生ずるコストに世界は耐えられるのか?
唐鎌 大輔

グローバリゼーションの次の世界、米国が目論むフレンド・ショアリングとは
地経学的分断の下、経済ナショナリズムに取って代わられる効率性と比較優位
菅原 淳一

受け入れざるを得ない悲しい現実、アジアの中でも「小国」に転落する日本
インドネシアにも抜かされる?日本は抜本的な意識の転換を
加谷 珪一

「持たざる国」日本の難題、世界の重要鉱物を牛耳る中国にどう対抗するか
中国に盗まれたレアアース技術、経済安全保障とインテリジェンスの強化が急務
日本戦略研究フォーラム

日本が主導したCPTPP、英国の加入決定はポストTPPにどんな影響を与えるか
経済規模以上に重要な戦略的価値、試される日本の構想力
菅原 淳一
本日の新着

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②
町田 明広

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影
生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に
小久保 重信

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか
【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略
小林 啓倫

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件
医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か
アン・ヨンヒ
経済観測 バックナンバー

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか
唐鎌 大輔

【原油ウォッチ】米国のベネズエラ攻撃、イラン大規模デモ…地政学リスク急上昇でも原油60ドル台を回復しない理由
藤 和彦

インド経済が日本を抜く?実は「過大評価」の可能性、雇用難が成長の足かせ…日本にはインド人材の確保にチャンス
藤 和彦

高市政権で復活したリフレ派が重視した「マネー」に意味はあるか?金利上昇局面の今だからこそ異次元緩和を振り返る
河田 皓史

5年目に突入した超円安局面、終止符を打つために最低限必要なのはリフレ思想の撤回と中立金利までの利上げ
唐鎌 大輔

【2026年の世界経済】投資競争がAIから全方位に、分断は深まり貿易摩擦激化…ポスト・グローバル社会の方向性鮮明に
中島 厚志