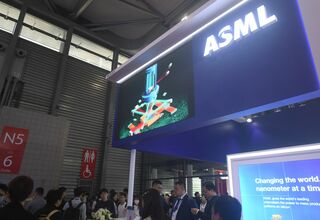私が通った小学校には、年に4回の遠足があった。そのうち、10月の秋の遠足の帰り道。夕陽の差す稲刈りの済んだ田圃の間の道を行くと、ふぁーっと向こうに飛び散っていく小さい影がある。イナゴだ。それも群れでいる。引率の先生も止めもしなかったから(それだけ周囲も寛容な時代だった)、私たちはその群れを田圃に入って追った。そして、イナゴを捕まえては持参したビニル袋につめていった。
帰宅後、パンパンに張ったビニル袋を母親に渡すと、大きな鍋に水を張り、そこにイナゴを放して素早く蓋をして、そのまま火にかけた。しばらく鍋の中からはイナゴが撥ねて鍋蓋や内側にポンポンあたる音がしたが、それもそのうちにしなくなった。
やがて、佃煮のように甘辛くなったイナゴが食卓に並んだ。カリッとした歯ごたえに、甘く、それをおかずにご飯がすすんだ。ただ、時々それまでの食感と違って、ぐじゃりとした苦く凄まじく不味い感覚が口の中に広がることがあった。イナゴの群れに混ざっていたバッタをいっしょに捕捉して、調理したものだった。食べるならイナゴじゃなきゃダメだ、と子ども心に知った。
絹糸をとった後に残る蚕の蛹も食べる
ハチの子も食べた。蜂の巣の中で蠢く白い幼虫だ。それもスズメバチともなれば、大きくて量も獲れる。ハチの子は佃煮や甘露煮のようにした缶詰もあるが、私の知る大人は、獲ったばかりをフライパンで煎って食べていた。因みに私は14歳の時にスズメバチに刺されたことがあるので、次に刺されたときにはアナフラキシーショックを起こすはずだ。
同じ長野県でも、私が生まれ育った長野市から南に下った諏訪湖の周辺では、蚕の蛹も食べた。もともと養蚕が盛んな地域で、ひと煮立ちさせて絹糸を取れば、当然のことながら中にある蛹が最後に残る。これを調理して食べる。貴重なタンパク源となる。