満たされている人こそ知るべき、座間市生活援護課の終わりのない困窮者支援
見えにくい困窮者を早期発見し、官民連携でサポートする「座間モデル」とは
2022.9.3(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

原発の警備員として働く61歳が紆余曲折の末に巡り会った理想の副業
【令和版おじさんの副業】放課後デイサービスの児童指導員
若月 澪子

イタコとともに消えゆく屋敷神「オシラサマ」とは何か
写真集『Talking to the Dead』:イタコのいる風景(5)
篠原 匡

「しあわせの量を増やす」売り上げゼロの老舗タオル会社を継いだ夫婦の考え方
伝統産業に新風を吹き込む丹後と「OLSIA」の誕生秘話【インタビュー編】
河合 達郎

2nm量産はこんなに困難、非現実的すぎて噴飯物の日本の半導体製造強化策
片や米国は約7兆円投入で中国に徹底対抗
湯之上 隆

統一教会信者のママ友も参加、なぜ韓国人はデモで物事を解決しようとするのか
「ごね得」が文化となっている韓国、声の大きい人間が勝つ国の思考回路
立花 志音
本日の新着

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件
医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か
アン・ヨンヒ

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影
生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に
小久保 重信

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか
【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至
唐鎌 大輔

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)
髙城 千昭
読書ガイド バックナンバー

「女性差別か、伝統か」今なお女人禁制が解かれない大峯山系・山上ヶ岳の歴史的背景とは
鵜飼 秀徳

あの富士山も「女人禁制」だった——立山、白山…なぜ霊山は女性を拒絶したのか
鵜飼 秀徳

読まれるメールや資料を作れる人とスルーされがちな人を分ける「たった一行」の差
武政 秀明

【関ヶ原の合戦の真実】石田三成は総大将ではなく、小早川秀秋は合戦前から東軍派、家康にも天下取りの野心はゼロ?
関 瑶子 | 高橋 陽介
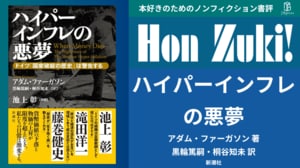
【書評】『ハイパーインフレの悪夢: ドイツ「国家破綻の歴史」は警告する』〜お金が紙くずになるとき
渡辺 裕子<Hon Zuki !>
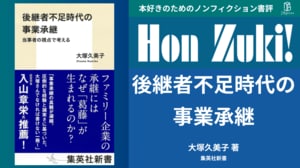
【書評】『後継者不足時代の事業承継』〜事業承継と女性のキャリア形成、「当事者」による葛藤についての論考〜
安川 新一郎<Hon Zuki !>



