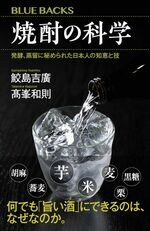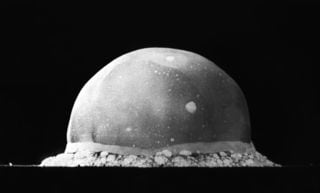どの蒸留酒とも違う東洋の摩訶不思議な酒、焼酎の謎をひもとく
高温で発酵しても味が落ちず、一度の蒸留で高濃度の酒ができる不思議
2022.5.14(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
本日の新着

県庁所在地なのに認知されていない「福島城」、近世城郭にして遺構も残る城の見どころ、かつて伊達政宗の祖父が隠居
日本「地味城」列伝(1)
西股 総生

「がんの一つや二つあって当たり前だろう」それでもやはり見つけられたくはない
勢古 浩爾

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴
【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには
小林 啓倫

小売りAI革命の分水嶺:エージェント型コマース巡るグーグルと小売り大手の主導権争い
共通規格の普及と専用チップで低コスト化を加速、消費者との絆を保つ新戦略が試される
小久保 重信
読書ガイド バックナンバー
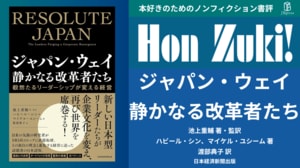
【書評】『ジャパン・ウェイ 静かなる改革者たち』〜世界は日本企業から何を学んでいるのか
黒田 由貴子 <Hon Zuki !>

「女性差別か、伝統か」今なお女人禁制が解かれない大峯山系・山上ヶ岳の歴史的背景とは
鵜飼 秀徳

あの富士山も「女人禁制」だった——立山、白山…なぜ霊山は女性を拒絶したのか
鵜飼 秀徳

読まれるメールや資料を作れる人とスルーされがちな人を分ける「たった一行」の差
武政 秀明

【関ヶ原の合戦の真実】石田三成は総大将ではなく、小早川秀秋は合戦前から東軍派、家康にも天下取りの野心はゼロ?
関 瑶子 | 高橋 陽介
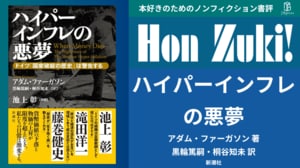
【書評】『ハイパーインフレの悪夢: ドイツ「国家破綻の歴史」は警告する』〜お金が紙くずになるとき
渡辺 裕子<Hon Zuki !>