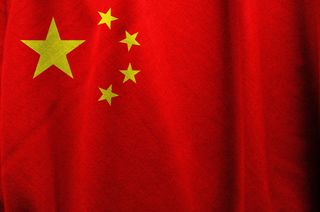(英エコノミスト誌 2021年9月11日号)
 庶民が中国共産党の意に沿わない言動をすれば容赦なくあの銃口が火を噴く
庶民が中国共産党の意に沿わない言動をすれば容赦なくあの銃口が火を噴く
ある日の早朝。かつて大物実業家として成功し、今は西側の国で暮らす沈棟氏のもとに祖国・中国から電話が入った。
相手は元妻の段偉紅氏。声を聞くのは4年ぶりだ。
段氏は2017年9月に北京で姿を消した。共産党の反汚職運動で、段氏の顧客に捜査の手が及んだ直後のことだ。
顧客は党中央政治局の若手で、一度は最高権力者・習近平氏の後継者と目された人物だった。
出版中止を懇願してきた元妻
ホイットニーという英語名も使っていた段氏は、その後もう一度電話をかけてきた。どちらの通話でも、伝えてきたのは警告の言葉だった。
1990年代から2000年代にかけて2人が起業家として一緒に活躍したことについて沈氏が著した本の出版――9月7日に予定されていた――を思いとどまるよう求めてきたのだ。
沈氏に言わせれば、あれは異常なほどの急成長と政治的地位を利用した口利きを特徴とする一種の金ピカ時代であり、そのおかげで沈氏と段氏、そしてビジネスパートナーたちの双方が大もうけした。
パートナーのなかには、共産党の高級幹部の家族も含まれていた。
「国家に逆らったところで、いいことは一つもない」。段氏は元夫にそう語りかけ、自分はいま仮釈放されているが、いつまた再勾留されるか分からないと明かした。
そして、沈氏と一緒に暮らす12歳の息子のことを考えてほしいと懇願した。
それでも沈氏は出版に踏み切った。本誌エコノミストが電話で行ったインタビューでは、「(あの電話の)相手が彼女だったのか、それとも彼女を裏で操る連中だったのか、よく分からない」と語った。
「本人は、この4年間、外の世界とは一切接触していないと言っていた」
沈氏はこの脅迫の試みについていろいろ考えているものの、共産党が本の内容を知っていたのか、それとも「私の人物像と私が知っていることを」を単に恐れていただけなのか、ピンとこないそうだ。