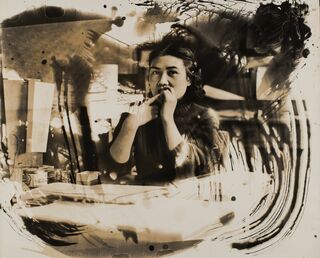このような結論の問題点は、IPCCのすべての報告書に共通している前提、すなわち「太陽は気候変動に関与しない」という前提によるものです。
もちろん、太陽は風や天候、地球上の生命にエネルギーを提供していますが「地球が受け取るエネルギーは大きく変わらないという前提」です。しかし、太陽も他の星と同じように活動が変化する星です。よく知られているのは、太陽の表面に見える黒点の存在で、その数は約11年の周期で変化しています。また、太陽活動はより長い周期でも変化します。例えば、小氷期の1645~1715年は黒点がほとんどない期間で、太陽の活動が低下していた時期と重なります。逆に西暦1000年前後は太陽活動が活発な時期でした。
太陽の活動が低かったり高かったり変化することは珍しいことではなく、過去1万年あまりで、太陽は高活動(黒点が多い)と低活動(黒点が少ない)の間を8~9回行き来しています。
太陽の活動が変化するたびに、気候にも変化があることがわかっています。その変化はけっして小さいものではありません。1000年前後の中世温暖期は、地球上で人類が繁栄していた時代でした。しかし、14世紀になると、今度は気候が悪化し、不作や栄養失調、疫病などの問題が発生し、人類は悲惨な状況に直面しました。小氷期の気候変化の大きさについては諸説ありますが、太陽活動が活発な時とそうでない時の気温変化は1~2℃であるという信頼のおける研究結果があります。また、中世温暖期や小氷期以前にも、気候変動と太陽活動との顕著な相関関係は過去1万年間に及びます。