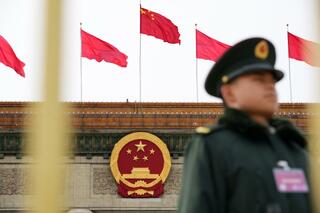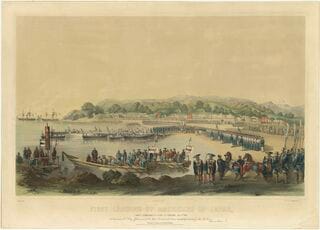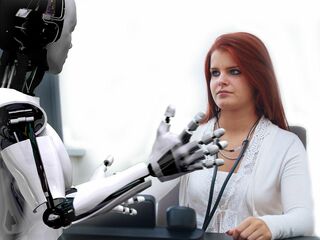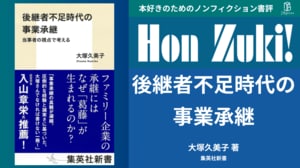炎天下での回収作業は、私たちの水分を容赦無く奪っていく。ただでさえ暑い変死用の装備の下は、噴き出した汗でびっしょりだった。猛烈に喉が渇いて脱水症状を起こしかけていたので、少し休憩を取ることにした。私は持参していたミネラルウォーターを半分飲み干した。中身はぬるくなっていたが、最高にうまかった。生き返ったような気がする。
山の景色を見ながら地べたに座っていると、風が通り抜けた。死臭が漂い、遺体からこぼれ落ちた蛆虫がそこら中でうごめく、お世辞にも快適な環境とはいえないが、私には山肌に沿って吹き抜ける風が心地よかった。
「いやぁ、この風は本当に気持ちいいですねぇ」
となりにいた若手刑事は、あきれた顔でつぶやく。
「えっ、まぁ・・・そうですね」
救世主の登場
次の難関は遺体の入った極楽袋を抱えて、どうやって山道を搬送するかだ。捜査車両が停めてある駐車場までは、かなり距離がある。ふたりで険しい茂みの中を運ぶことになれば、2時間以上はかかるだろう。
現場は無線も携帯電話も圏外なので、応援を呼びたくても連絡手段がない。いったん私たちだけが駐車場までもどり、署に連絡して応援を待つ時間もなさそうだった。山の夜は早い。すでに夕方になろうとしていた。
こうなれば、ふたりで運ぶしかない。